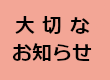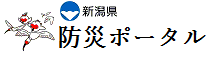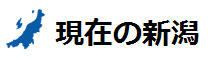本文
酸性雨について
1.酸性雨とは
酸性雨とは、主として石炭や石油の燃焼により生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物などが大気中で硫酸や硝酸などに変化し、これを取り込んで生じると考えられるpH(ピーエイチ)5.6以下※の雨のことを言います。広い意味では、雨のほかに霧や雪、さらにガスやエアロゾル(微粒子)の形で地表に到達する現象も酸性雨に含められます。
※標準的な大気中の二酸化炭素(360ppm)が飽和状態となるまで水に溶けた時のpHが5.6となります。
2.酸性雨の監視体制
(1)県による定点観測
県では県内2地点で降水のpH等の調査を行っています。県内における降水pHの年間平均値は過去5年間で4.9~5.1でした。
また、酸性雨調査の結果を5か年ごとに取りまとめています。
- 新潟県酸性雨調査報告書(平成27年度~令和元年度) [PDFファイル/2.77MB]
- 新潟県酸性雨調査報告書(平成22年度~平成26年度)[PDFファイル/8.33MB]
- 新潟県酸性雨調査報告書(平成17年度~平成21年度)[PDFファイル/2.25MB]
- 新潟県酸性雨調査報告書(平成12年度~平成16年度)[PDFファイル/1.7MB]
(2)国による定点観測
国では、令和6年現在、全国で酸性雨対策のための調査を実施しており、新潟県内では以下の調査を行っております。
- 佐渡市関岬に酸性雨観測用の測定所を設置し、降水のpH等の調査を行っています。
- 村上市三面において、酸性雨が土壌や生態系に与える影響を調査しています。
詳しくは環境省のホームページへ<外部リンク>
また、平成10~25年度には、佐渡市真更川の山居池(さんきょいけ)にて「酸性雨モニタリング(陸水)調査」を実施しました。当該調査は、国の委託を受けた新潟県が実施したもので、その結果を以下のとおり取りまとめました。
新潟県酸性雨モニタリング(陸水)調査報告書(平成10年度~平成25年度)【出典:環境省】 [PDFファイル/17.4MB]
(3)東アジアにおける国際的な取組
新潟市西区曽和に「アジア大気汚染研究センター」が設置されています。当該センターは東アジアの13カ国が参加する「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)」のネットワークセンターとして技術的な中核を担っています。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)