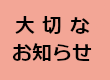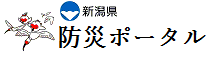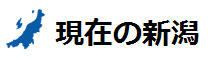本文
実需ニーズに応える大豆生産で安定した販路を確保 こだわりの味噌加工で地域の大豆需要を支える【農事組合法人 竹直生産組合】

(農)竹直生産組合の皆さん
法人の概要
上越市吉川区で、平成8年に集落農地の維持・発展を目的に設立された集落型法人です。水稲・大豆の生産に加え、平成14年には味噌加工、平成18年には園芸部門を設立し、複合経営に積極的に取り組んでいます。
平成27年度全国豆類経営改善共励会において農林水産大臣賞(集団の部)を受賞しました。
経営面積・品種と内訳(平成30年産)
| 作目 | 品種 |
作付面積 (ha) |
収量 (kg/10a) |
品質 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 里のほほえみ | 5.1 | 170 | 2等以上 39 |
| シュウリュウ | 4.0 | 142 | 〃 88 | |
| 青大豆 | 4.4 | 147 | 〃 0 | |
| 黒大豆 | 2.0 | 95 | 〃 0 | |
| 水稲 | コシヒカリ等 | 65.0 | ― | 1等級 78 |
| 園芸 | ブロッコリー等 | 2.0 | 1,700 | A品 100 |
大豆作の概要
| 工程 | ポイント |
|---|---|
|
ほ場準備 |
・水稲2年-大豆2年のブロックローテーション |
|
耕起 播種 |
・施肥は、耕起前に石灰質資材及び速効性肥料(N-P-K=14:8:8)を散布 |
|
防除 |
・雑草防除は、耕起前の非選択性除草剤の全面散布、生育期のロータリカルチによる2回の中耕培土の他、除草剤(ポルトフロアブル、大豆バサグラン液剤)を散布 |
|
収穫 |
・収穫は同地区の組織に委託 |
インタビュー ~(農)竹直生産組合 平田さんにお話を伺いました~
― 大豆に関する取組について教えてください。
「大豆生産の他、味噌の加工・販売も行っています。」
大豆の生産は法人設立前から行っており、設立後に作付を拡大し、現在は約15haとなっています。生産した大豆は、JAを通じ、市内の豆腐加工業者等へ販売している他、当法人の味噌加工にも使用しています。
加工を始めた動機は、冬期の仕事確保でした。法人化後に2名を雇用しましたが、農閑期には仕事が少なかったため、当地域の酒造りの技術を活かし、味噌加工ができないかと考えました。幸い、地元の杜氏の方から麹の作り方を教わることができ、加工を始めることができました。原材料の米は五百万石、大豆は里のほほえみで全て当法人で生産したものを使用しています。

△ 味噌加工の様子
― 多収のために工夫していることについて教えてください。
「条件に応じて播種方法の変更や丁寧な弾丸暗きょの施工を行っています。」
ほ場や天候条件により播種方法を変えています。湿害が発生しやすいほ場では、畝立て播種を行っていますが、排水の良いほ場や播種後に無降雨が続く予報の場合には、乾燥による出芽の遅れが生じないよう平畦で播種しています。また、排水性を高めるため、大豆作付けほ場には、全ほ場に5mおきの間隔で、弾丸暗きょを施工しています。

△ 耕うん同時播種(平畝)の様子
― 省力化のために工夫していることについて教えてください。
「2年連作による耕うん作業の効率化や多品種栽培による作期分散を行っています。」
大豆2年+水稲4年のローテーションを組んでいます。当地域の土壌は重粘土であるため、大豆作1年目は作業速度が遅く、砕土率もそれほど高まりませんが、2年目は作土がこなれて、耕うん等の作業効率が上がり、省力化に繋がっています。連作障害や雑草の増加を防ぐため、3年以上の連作は避けています。
品種構成もポイントです。実需の要望で早生のシュウリュウを導入している他、晩生の里のほほえみ、青大豆、黒大豆と作期分散できる品種構成とすることで、無理のない作業体系としています。
― 大豆関連事業の今後の方針について教えてください。
「味噌加工施設を新設し、増産と作業の効率化を進めます。」
実需ニーズに基づき、大豆の作付品種を選定していますが、今後もニーズに応じた生産を継続します。
味噌加工については、増産と作業の効率化を進めていきたいとの思いから加工施設を新設しました。今後は、商品ラインナップも増やしていきたいと考えています。
※経営面積や品種情報については取材時のものです