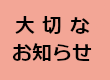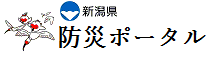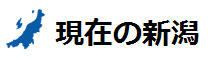本文
12月13日(金曜日)に令和6年度「居住支援勉強会」を開催しました
開催概要

- 開催日時:令和6年12月13日(金曜日) 14時00分~17時00分
- 会場:新潟県自治会館 別館 9階 ゆきつばき
- 開催概要
(1) 居住支援等に関する制度説明・取組紹介
講師:国土交通省北陸地方整備局、厚生労働省関東信越厚生局、新潟県
(2) 基調講演「地域の支援体制のつくり方 ― 新時代の居住支援に向けて」
講師:日本大学文理学部社会福祉学科 白川泰之 教授
(3) 事例紹介「岡崎市における居住支援協議会の設立と居住支援の取組について」
講師:愛知県岡崎市福祉部ふくし相談課 永田 享之 係長
愛知県岡崎市都市基盤部住宅計画課 増澤 翔太 主査
(4) 座談会「地域社会と連携した支援体制の構築に向けて」
ファシリテーター:新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 中村 健 准教授
コメンテーター:日本大学文理学部社会福祉学科 白川泰之 教授
愛知県岡崎市福祉部ふくし相談課 永田 享之 係長
愛知県岡崎市都市基盤部住宅計画課 増澤 翔太 主査
当日の様子
基調講演「地域の支援体制のつくり方 ― 新時代の居住支援に向けて」
基調講演では、「地域の支援体制のつくり方 ― 新時代の居住支援に向けて」と題して、日本大学文理学部社会福祉学科 白川泰之 教授より、福祉・住宅の歴史や政策、それぞれの視点からみた現状や課題、これらを踏まえて、今後の居住支援における住宅・福祉の連携に向けて居住支援にまつわる言葉やイメージを関係者で共有する「共通言語化」の重要性についてご講演いただきました。「共通言語化」には、居住支援にまつわるコトを関係者で共有し積み重ねることで、居住支援の体制が作られていく、といったご説明もあり、協議会の設立に向けたヒントをいただきました。
事例紹介「岡崎市における居住支援協議会の設立と居住支援の取組について」
事例紹介では、「岡崎市における居住支援協議会の設立と居住支援の取組について」と題して、愛知県岡崎市における居住支援協議会の設立までの経緯や、岡崎市が取り組む「住まいサポートおかざき」や岡崎市版「住まい支援システム」について発表していだたきました。岡崎市版「住まい支援システム」では、住宅確保要配慮者からの相談について、住宅・福祉の双方が一緒に相談を受け、福祉部局で配置される「住まい連携推進員」が支援プランを作成し、関係機関や市内部と連携・調整しながら、入居支援と居住継続支援の一体的な提供を行っており、住宅部局と福祉部局が連携した取組もご紹介いただきました。
座談会「地域社会と連携した支援体制の構築に向けて」
座談会では、「地域社会と連携した支援体制の構築に向けて」と題して、新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 中村 健 准教授から司会をしていただき、参加者からは「市町村協議会の設置へのメリットは?」「孤独死への対応は?」などの質問に対して、白川教授からの意見や岡崎市での取組事例の紹介していただきながら、居住支援体制を構築することの大切さを共有しました。
会場の様子
当日は、行政職員・福祉団体・不動産会社などから99名(うち、オンライン参加64名)参加していただきました。
参加された方からは、「岡崎市の取組を見習いたいと思った」「本日の勉強会をきっかけに県内の取組を検討していくことが大事」「居住支援の取組事例をさらに知りたくなった」などといった感想のほか、多くの御意見をいただきました。 こうした声も踏まえて、県内の居住支援の促進に取り組んでいきます。