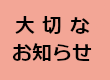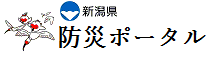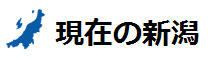サイト内検索
ページ番号を入力
本文
森林研究所たより ナメコに最適なオガ粉はどれ?(林業にいがた2017年9月号記事)
1 はじめに
本県は、菌床ナメコ生産で全国トップレベルですが、その生産に不可欠なオガ粉の大半を県外に依存しており、東日本大震災による東京電力福島原発事故の影響でオガ粉の供給が不安定になっています。
そこで、森林研究所では、平成25年度から28年度に渡り、オガ粉の安定供給と県内に分布する広葉樹資源の活用を図るため、ナメコ菌床栽培に適したオガ粉の樹種について研究を進めてきました。
2 樹種単独での試験
- 試験した樹種
昨年8月号で報告した、オニグルミ等16樹種に加えて、新たにニセアカシア、ケヤキ、クヌギ、ヤマザクラの4樹種で実施し、合せて20樹種のデータを取ることができました。 - 調査方法
菌床栽培用に市販されている広葉樹オガ粉を対照区として使用し、当所で通常行っている栽培条件で比較栽培試験しました。
調査の内容は、1収量(1番、2番収穫の合計)、2栽培日数(発生処理から収穫終了まで)、3きのこの形質としました。 - 栽培結果
対照区と比較して収量が多いこと、栽培日数が同程度か短いこと、形質に問題がないことの3つの条件をクリアできたのは、クヌギ(写真1)で、ブナ、アオダモ、イタヤカエデ、ハクウンボクと同様、ナメコ栽培に適した樹種であることが判りました。(表1)
表1 樹種単独で使用した場合の結果
| 対照区より良い【◎】区分 | 対照区と同程度【○】区分 |
|---|---|
|
(調査項目すべてで良い)
|
(収量多いがきのこの形質に難あり)
(対照区と同程度)
|
| 対照区に比べ若干劣る【△区分】 | 対照区に比べ劣る【×区分】 |
|---|---|
|
(収量若干少ないが他は同程度)
|
(調査項目すべてで劣る) |
※★樹種名★の記載は、今回試験した樹種

写真1クヌギからの発生状況
3 コナラと混合した試験
- 試験した樹種
栽培結果が対照区より良い◎区分、または、対照区と同程度の〇区分で、かつ、オガ粉工場へ入荷量の多い、イタヤカエデ、ブナ、ホオノキの3樹種についてコナラとの混合試験を行いました。なお、コナラについては、粒度(細、粗)の違いについても試験しました。
調査方法は樹種単独での試験と同様です。 - 栽培結果
樹種単独の場合と同様に、3つの条件をクリアできた組合せが判りました(表2)。その時の発生状況は写真2のとおりで、コナラと3樹種いずれとの混合でもナメコ栽培適性があり、粒度が粗粒の場合に収量が良い傾向でした。
県内に広く分布し蓄積量の豊富なコナラと入荷量の多いホオノキはともに、ナメコ菌床栽培に利用できることが判りました。

写真2 コナラとイタヤカエデ混合からの発生状況
表2 混合試験の結果
| コナラの割合 | コナラの粒度 | 組合せる樹種 | 収量の多い順 |
|---|---|---|---|
| 50% | 粗粒 | ブナ50%もしくはイタヤカエデ50% | 1 |
| 50% | 細粒 | ブナ50%もしくはイタヤカエデ50% | 2 |
| 50% | 粗粒 | ホオノキ50% | 3 |
※粗粒を使用した場合、細粒より収量が多い傾向
※市販の広葉樹オガ粉は、通常細粒で流通
4 オガ粉の利用拡大に向けて
今回の試験結果について説明したパンフレットを作成しますので、多くの皆様からご覧いただき県内産広葉樹オガ粉の利用拡大につなげたいと考えています。
きのこ・特産課 倉島 郁