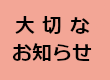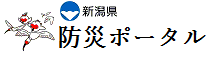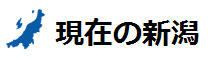本文
令和5年度中山間地域活性化シンポジウムを開催しました。
令和6年3月7日(木曜日)に、「未来につなげる地域づくりを目指して」をテーマに、地域住民が主体となった活動を続けられる体制づくりや、継続して活動していくためのコツについて理解を深めることを目的に、中山間地域活性化シンポジウムを開催しました。
地区の事例発表
事例発表1 柏崎市南鯖石地区 南鯖石コミュニティセンター
発表者:石塚 雄一郎 様

【地域の取組概要】
・若者、女性を含む幅広いメンバーを参集し、コミュニティセンター専門部会員を中心に、農業・福祉・移住定住促進の分野ごとの検討を行い、将来プランを策定。
・将来プランに基づき、多様な人材との連携による生産体制の構築、集落協定の広域化、移住定住者の確保に向けた取組を開始。
【主な発表内容】
・4つの集落協定で広域化し、広域加算とコミュニティ協議会の活動を併せた地域活動を展開。
・令和3年度からはビレッジプランに取り組み、多様な人材の活躍による新たな農業生産体制として「農福連携協議会」の設立に向けた取組や、移住・定住の促進に向けた、新規就農者と地域住民との交流会イベント等の取組を実施。
事例発表者2 富山市黒瀬谷地区 黒瀬谷KIRARI活性化協議会
発表者:宮田 好一 様

【地域の取組概要】
・平成30年度に、今後10年間の黒瀬谷地区の将来像とその課題解決に向けた「黒瀬谷地区活性化アクションプラン」を取りまとめ、令和元年度にプランを実行するための「黒瀬谷地区活性化プラン推進委員会」を組織。
・黒瀬谷地区の特色ある地域づくりを発展・維持できるように、5つのプロジェクトチームに分かれ、コミュニティビジネスの創出による雇用や所得の拡大、定住促進に取り組んできた。
・令和5年4月には、推進委員会を「黒瀬谷KIRARI活性化協議会」として再構築し、農村RMOに向けた取組を開始。
【主な発表内容】
・黒瀬谷地区活性化アクションプランの元、米やシャクヤク、カブトムシやクワガタといった、地域資源を活用した体験交流活動の展開や、月1回の直売イベントで20年間続いている「菜菜(さいさい)こられ市」を運営。
・令和2年以降のコロナ禍の影響を受け、大半の恒例行事が中止したことで活動が低迷。地区の活気に陰りが出てきたことを受け、令和5年から農村RMOに向けた活動を開始。
・住民アンケートやワークショップにより、改めて地区の課題を整理し、地域の目指す姿である将来ビジョンを作成した。
パネルディスカッション
テーマ:地域づくり活動を続けていくためのコツ
コーディネーター:藤山 浩 様(一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所)

・昭和34年島根県益田市生まれ。一橋大学経済学部を卒業し、島根県立大学連携大学院教授、島根県中山間地域研究センター研究統括監等を歴任。
・平成29年に「一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所」を設立し、地域分析、 地域づくり支援などで全国を回る他、国・県の委員を多数引き受ける。
・令和4年には「上越市創造行政研究所」所長に就任
パネリスト
|
石塚 雄一郎 様 南鯖石コミュニティ センター ワイワイ里山振興部 会長 |
宮田 好一 様 黒瀬谷KIRARI活性化 協議会 会長
|
大島 晃 様 黒瀬谷KIRARI活性化 協議会 事務局長
|
浮須 崇徳 様 NPO法人ヨリシロ 代表
|
テーマに基づいた下記の4つの話題について、キーワード方式を用いてディスカッションし、理解を深めました。
話題1 活動体制づくりの進め方とそのための人材確保のやり方
| 回答者 | キーワード | 内容 |
|---|---|---|
| 石塚 | コミセン活動 | ・集落協定だけでなく、コミセン活動と絡めて行う。 ・農福に取り組み始めるので、それをきっかけとして、外から来て働いてくれる人と地域を繋いでいきたい。 |
| 宮田・大島 | 無いなら外から補完 | ・イベントでは大学生の力を借りたり、必要に応じて知見のある地域外の人と連携したり、集落内で完結できない取組は外部の力を借りる。 (例)スイーツ作り→近くの地域在住のパティシエの方を講師に呼ぶ。 ・やる気を持って地域に来てくれる人なら誰でも受け入れて、一緒にやってみて、その人に続けるかどうかを判断してもらうようにしたいと思っている。 |
| 浮須 | コミュニケーション 計画的継続 |
・複数の集落で活動を進めていくには、定期的にコミュニケーションをとり「この取組はこのためにやっている」という目的意識の共有が大切。 ・その際、地域の課題を外に向けても発信していく=課題びらき。それが出会いにつながることもある。 |
| 藤山 | コンマX | ・フルタイムじゃなく、1週間及び月に1回というような、1ではなくても0.1(コンマ)で活動に関係してくれる人をうまく取り入れることで、裾野の広い人材確保に繋がる。 |
話題2 活動資金を確保する仕組みづくり
| 回答者 | キーワード | 内容 |
|---|---|---|
| 石塚 | 直払 | ・地域で稼ぎ出すものが無いので、中山間直払の広域加算を活動の資金源にしている。 ・広域化する際は、協定で使えるお金と地域で使うお金を試算した上で協定へ説明に回り、理解を得られた協定で広域化した。 ・今後、ビレッジを通じ、稼げる仕組みに結び付けることを考えていかないとと感じている。 |
| 宮田・大島 | 稼げる地域づくり | ・大前提として、県、市と情報共有して、補助事業に対するアンテナを高めておく。 ・それに加えて、今の活動を更に稼げるようにブラッシュアップしていく。 (例)農産物直売 → 加工して販売 → 加工品のブランディング(人気度・知名度の向上) |
| 浮須 | Minimum・Viable・Product開発 | ・ビジネス、商売を始めるときの手法。 ・小さく始めて、世に送り出して、アップデートするというサイクルを回しながら、軌道に乗ったものだけを残していく。 |
| 藤山 | 連結決算 | ・異なる部門や組織をつなげて決算する。 ・地域で一番お金が使われているのは介護と医療。地域活動で色んな人の活躍の場ができて「おたっしゃ=元気」になれば、それだけでお金が浮いていることになる。 ・全部の事業が黒字にならなくても、どこかで安定した収入があることが重要。 |
話題3 息切れしない進め方や後継者に繋げるために必要なこと
| 回答者 | キーワード | 内容 |
|---|---|---|
| 石塚 | 活動のまとめ | ・新しい取組を始める際は、地域にある他の協議会の活動に似た部分があればくっつけてしまう。 ・役と負担を増やさないように活動を束ねることを意識。 |
| 宮田・大島 | 心に火をつける | ・志をしっかり共有し、お互いモチベーションを高めながら継続的に取り組んでいくということが大切。 ・若い人を講師にしてみる等、色んな切り口から攻めることで効果が出ることもある。 |
| 浮須 | 地域と若者がともに育み合う | ・外部人材を受け入れる際は、地域側ばかり良いことがあっては長続きしないので、地域にも若者にもWin-Winの関係が良い。 ・地域の人も、若者と一緒に勉強していくんだという考え方で受け入れられると良い。 |
| 藤山 | 地域経営会社 | ・農業をやりつつ、交通、福祉もやるという他業展開の会社を立ち上げ、連結決算で従業員が食べていけるような体制をつくる事例が増えてきている。 ・一人では神輿は挙がらないので、地域で会社を作って、その中で頑張ってもらうやり方。 |
話題4 今後の抱負を「漢字一文字」で
| 回答者 | 漢字一文字 | 内容 |
|---|---|---|
| 石塚 | 継 | ・今を維持し、いかに繋いでいくかを大切にしたい。 |
| 宮田 | 気 | ・自分でできるだけ元”気”を保って、やる”気”をつくりたい。 |
| 大島 | 躍 | ・中山間地の活性化の取組を今までベースで取り組んでも、疲弊す るペースのほうが勝っているように感じている。ここはもうひと踏ん張り、勢いよく自ら動き回る。 |
| 浮須 | 楽 | ・長く続けていこうと思った時には、楽しめるかが大事。楽しいと続けていけることを実感しているので、地域の皆さんも楽しんで取り組んでいけると良い。 |
| 藤山 | 姿 | ・中山間地域は今、夜明け前の厳しさで、2020年代が勝負になる。 ・諦めずに頑張った姿というのは、その後に続く世代が見ていて、その世代が同じ年になった時の勇気になるのではないか。 |
過去の開催状況
過去の開催状況については、下記リンクからご確認ください。