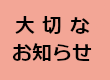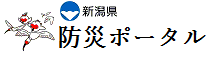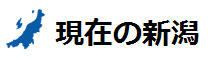本文
新潟県の外来種について
外来種とは
外来種とは、もともと生息・生育していなかった地域に、意図的又は非意図的に人間の活動によって持ち込まれた生物のことをいいます。
新潟県では、生態系や私たちの暮らしに影響を及ぼすおそれのある外来種について、皆さんに知ってもらうこと、啓発活動や外来種対策に活用することを目的に外来種被害防止パンフレットを作成しました。

新潟県外来種被害防止パンフレット2025年版 [PDFファイル/9.26MB]
次の外来種を見かけたら
以下の3種は、新潟県内での捕獲事例が少ない又は新潟県内で発見されていないものの、人の身体や生活環境、農林業への被害が懸念される種であり、早期発見・早期防除を図る必要があります。
目撃したら、新潟県またはお住いの市町村の外来生物担当課までご連絡をお願いします。
-
新潟県の連絡先 新潟県環境局環境対策課自然共生室 自然保護係 Tel:025-280-5151
1 アライグマ
- 咬まれたり、ひっかかれたりするおそれがあります。近づいたり、触ったりしないでください。

2 セアカゴケグモ
- 毒腺があり、咬まれると痛みや腫れ、時に重篤な反応(アナフィラキシーショック)が起きることがあります。

3 クビアカツヤカミキリ(県内未確認)
- 福島県や群馬県などで分布を広げており、新潟県内に侵入すると果樹やサクラ並木等に被害のおそれがあります。
- クビアカツヤカミキリの幼虫4月から10月かけて活動し、「フラス」というフンと木くずが混ざったものを木の幹に開けた穴から排出します。


特定外来生物について
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、平成17年6月1日施行)により、国は、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を及ぼすおそれのある海外起源の外来種を特定外来生物として指定しています。
特定外来生物に指定された生物を、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止されています。

特定外来生物を無許可で飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)したり、許可を受けていない人に譲渡等をした場合は、法律により罰せられるのでご注意ください。
また、特定外来生物を野外において捕まえた場合、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりませんが、新潟県内の河川・湖沼ではブラックバス類とブルーギルを再放流(リリース)することは、新潟県内水面漁場管理委員会の指示(平成11年12月28日新潟県内漁場管理委員会指示第1号)により禁止されています。
※法律・政令・規則・告示等の全文はこちら(環境省ホームページ)<外部リンク>
※特定外来生物一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>
※新潟県内水面漁業管理委員会指示(平成11年12月28日)
条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について
「条件付特定外来生物」は、特定外来生物の規制の一部が適用されません。令和5年6月に、アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。
この2種は、採集や飼育は禁止されていませんが、販売や野外に放すことは禁止されています。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。
特定外来生物の飼養等を開始する場合には
特定外来生物を飼養等することは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、許可を得ることで飼養等することが可能です。
なお、特定外来生物として規制された後に、新たにペット・観賞の目的で飼養等することはできません。
-
特定外来生物に関する問合せ先、申請先
詳しくは、下記までお問い合わせください。
環境省 関東地方環境事務所 Tel:048-600-0817(野生生物課)
環境省 自然環境局野生生物課 Tel:03-3581-3351(内線6987)
外来種に関すること
上記のほか、外来種について紹介します。
ヒアリとアカカミアリ(要緊急対処特定外来生物)
下記リンク先をご覧ください。
特定外来生物【ヒアリ】について
特定外来生物【アカカミアリ】について
アライグマ(特定外来生物)
- 北アメリカ~中部アメリカが原産地の外来種です。
- 主に夜間に活動し、水辺に近い場所を好みますが、家屋や寺社の屋根裏などで繁殖することがあります。
- 前足の指が器用で、スイカをくり抜いて食べたり、トウモロコシの皮をむいて食べたりするほか、両生類や鳥類なども幅広く捕食し、生態系にも影響があります。
- また、人や在来の動物と共通の感染症を媒介するおそれもあります。
新潟県では、アライグマによる生態系や生活環境被害の早期防除を図るため、「新潟県アライグマ防除実施計画」を策定しています。下記リンク先をご覧ください。
セアカゴケグモ(特定外来生物)
下記リンク先をご覧ください。
オオカワヂシャ(特定外来生物)
- ヨーロッパ~アジア北部が原産地の外来種です。
- 日当たりの良い水路、河川、湿地の水際などを好み、在来のカワヂシャと雑種をつくります。
- 県内でも在来種のカワヂシャが本種に置き換わっていることがあり、4月~9月に開花し、ちぎれた葉や根茎でも増える繁殖力が強い種です。
オオフサモ(特定外来生物)
- 南アメリカが原産地の外来種です。(写真提供:井上信夫氏)
- 池沼、ため池、河川、水路など、比較的閉ざされた環境で局部的に発生することが多い種です。
- 元々生えていた水草の生育場所が奪われたり、水質や流れを悪化させたりします。
- 県内では阿賀野川水系の下流域で確認されています。
- 環境省関東地方環境事務所ホームページ<外部リンク>
- 人と自然の共生に関する情報一覧
- 環境省 外来生物対策ホームページ<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)