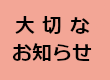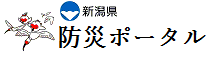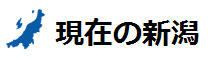ページ番号を入力
本文
学びいきいき中越第87号
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて
各学校においては、今年度の県の学校教育の重点を受け、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が着実に進められていることと思います。
昨年度の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の集計結果では、「課題解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む」、「話し合う活動を通じて、考えを深めたり、広げたりする」の質問事項に肯定的回答をした管内の児童生徒の割合はいずれも8割となり、全国平均を上回っています。一方で、「その教科の勉強が好きか」という質問事項に対する児童生徒の肯定的回答の割合は高くありませんでした。各学校での授業改善の取組の成果が、「主体的・対話的で深い学び」を実現する児童生徒の姿として現れてきていますが、「学ぶ楽しさを実感する」という点では課題があります。
学校教育の重点では、授業改善の取組事項の一つとして「『学ぶ楽しさ』『分かる喜び』が実感できる授業づくりに全校体制で取り組む」が挙げられています。「学ぶ楽しさ」「分かる喜び」を実感するためには、学習の目的・目標を児童生徒が共有し、自分の学びを認識・評価できるようにすることが大切です。見通し・振り返りの学習活動を全校で共通に取り入れるなどして、児童生徒が「授業の内容も分かるし、その教科の勉強も楽しい」と実感できるような授業づくりに全校体制で取り組みましょう。
Web配信集計システムを活用して授業改善を
「知識・技能を活用する力に課題がある」という本県の学力実態を踏まえ、今年度からWeb配信集計システムは、基礎的・基本的な「知識及び技能」の習得を目指したステージから、「思考力、判断力、表現力等」の育成を目指す新たなステージへ移行しました。
「思考力、判断力、表現力等」を育成するために、日常の授業改善が求められています。自校や自学級の傾向を分析するための「結果分析シート」と「授業改善サポート」が教育支援システム上にも掲載されています。これらを活用して、次のように授業改善を進めていきましょう。
1 結果を分析する
昨年度までは、授業改善のために、県全体の傾向として正答率の低い問題を分析し、「解説・サポート問題」を配信してきました。本年度は「サポート問題」の配信は行わず、代わりに「結果分析シート」を掲載しています。シートはエクセル形式となっており、数値を入力すると小問ごとの正答率、誤答率、無答率が表示されます。目の前の児童生徒にとって最良の方策を見つけるためにシートを活用し自校や自学級の分析を行ってください。
2 日常の授業に生かす
「授業改善サポート」は、児童生徒に付けたい力を育成する学習過程の一例を示しています。授業を構想する際に大切な「見通し」と「振り返り」の場面が明記され、授業改善のポイントを具体的に分かりやすく示しています。自校や自学級の実態に応じてアレンジし、指導計画に取り入れるなど、日常の授業の充実に役立ててください。
いじめを「認知」する取組、虐待への対応を!
 |
平成29年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果によると、県内で発生した小・中学校のいじめの認知件数は、17,221件(前年9,706件)と大幅に増加しています。各校において、教職員がいじめを見逃さないよう、いじめの積極的な認知に努めたことが増加の原因と考えられます。しかし、学校間で、いじめの認知についての格差が見られます。いじめの「発見」を「認知」に結び付けるためには校内において点検、工夫することが大切です。 |
|
|
一方、千葉県野田市の虐待事案を受け、「児童虐待防止対策強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化が閣議決定されました。併せて、文部科学省は「学校・教育委員会等向け虐待対応手引き」を作成、公表しました。教職員が児童の目線に立ち、児童生徒のSOSを鋭敏に受け止め、児童生徒の命を守る対応が必要です。そして、虐待を認知した場合は迷うことなく、直ちに市町村教育委員会への報告及び児童相談所への通告をお願いします。
「考え、議論する道徳」取組のポイント
今年度から中学校でも全面実施されている「特別の教科道徳」ですが、管内では意欲的な取組が見られます。成果が見られる学校の取組のポイントを2つ紹介します。
1 評価の工夫…全校体制、学年体制で協働する取組
学習指導要領には道徳科の評価の工夫に関する例の1つとして、教職員同士で授業を見合うなど、チームとして取り組むことで児童生徒の理解を深め、変容をつかむことが挙げられています。各学年ごとに評価のために集める資料や評価方法等を明確にしておくことや、評価の視点などについて教師間で検討し、共通認識をもつことなども、学習評価の妥当性、信頼性等を担保することにつながります。
2 年間指導計画や別葉の作成・見直し
学習指導要領には「主題の配列に当たっては、主題の性格、他の教育活動との関連、地域社会の行事、季節的変化などを十分に考慮することが望まれる。」とあります。また、特別活動と道徳科のそれぞれの役割を明確にしつつ、連携を一層密にした計画的な指導を行うこと、児童生徒や学校の実態に応じて内容項目の指導時数を増やし、一定の期間をおいて繰り返し取り上げることなど、年間指導計画作成上の創意工夫について書かれています。計画を活用しやすいものとし、指導の効果を高めるようお願いします。
児童生徒の事故防止と安全指導を ~平成30年度児童生徒にかかわる事故発生状況~
|
交通事故では、幸い死亡事故の発生はありませんでしたが、小学生中学生ともに自転車乗車中の重傷事故が複数発生しました。スピードを出したまま信号のない交差点に侵入し、乗用車と衝突し頭部を損傷する重大事故もありました。また、歩行中の事故が依然多く発生しています。青信号の横断でも右左折車への注意をする他、日頃から危険な場所の確認をしておくことも事故防止につながります。 |
 |
|
|
スクールカウンセラーの有効活用を!
昨今の不登校、いじめ問題、暴力行為等の問題行動が急増している現状と学校規模に関わらずこれらの問題は発生するという点から、県では、今年度より「スクールカウンセラー等配置拡充事業」として全公立小・中・義務教育・特別支援・高等学校にスクールカウンセラー(以下SC)を計画配置しました。小中連携の観点から中学校区を基本とする配置となっています。SCは公募制とし、適任者を選考、採用しました。
SCは、臨床心理士等の資格を有する児童生徒の心理に関して高度で専門的な知識及び経験をもち、「心の専門家」と言われています。各学校で「チーム学校」の一員としてSCを校務分掌に位置付け、教育相談体制の充実を図るようお願いします。今回初めてSCが配置となった学校もあり、「SCをどのように活用したらよいのか分からない」という声をお聞きしました。事業開始から3か月が経とうとしていますが、SCの職務と活用例を紹介しますので、SCの有効活用をお願いします。
社会教育の窓
地域と学校の連携・協働に係る研修会

前半の新潟市食育・花育センター長の真柄正幸様の講義では、地域と学校との連携に関する基本的な考え方や、実践例をもとにした具体的な取組の進め方が紹介されました。後半は4~5名のグループに分かれて演習を行い、「地域連携担当教員の役割」や「地域を知り、地域の教育資源をどう活用するか」について活発な意見交換が行われました。最後に数グループから発表していただき、研修内容を共有し、深めました。
7~8月には管理職対象の「地域とともにある学校づくり研修会」を開催します。特に、新任校長の皆様から積極的に御参加いただき、持続可能な地域との連携や人口減少社会に対応できる学校づくりに生かしていただきたいと考えています。
管理手帳 中越版 ◇懲戒免職処分、懲戒処分事案0に向けて!◇
今年度4月からの事故報告件数は9件で、昨年度同時期より2件増となりました。特に、平成29年度から交通加害事故が続発し、憂慮すべき状況です。今年度に入ってからは、集中力の低下による前方不注意や赤信号の見落としによる交通加害事故が発生しています。自身の体調管理に留意するとともに、「車は、人の命を奪う凶器にもなり得る」との認識を強くもち、危険への想像力を豊かにした「かもしれない運転」の励行をお願いします。引き続き、交差点では、速度を落とし、左右の安全確認を徹底してください。
次に、昨年度末に行われた体罰に関する調査では、不適切な指導と判断された事例が17件(小11件、中6件)報告され、児童生徒の人権、人格を傷つけるような言動が後を絶ちません。具体的な事例から互いに学び合い、日々の指導を振り返る場を設定し、全校体制で体罰や不適切な指導を根絶するようお願いします。
今後も、非違行為根絶に向けた年間研修計画に工夫、改善を加え、県民、地域、保護者からの信頼を得るよう取組の継続・強化をお願いします。
 |
|
|
|