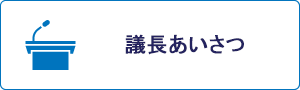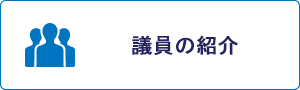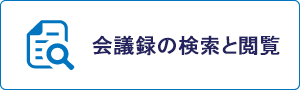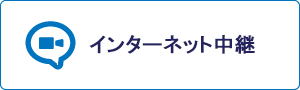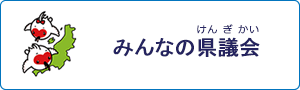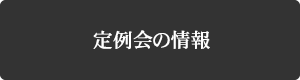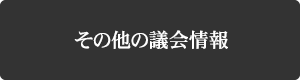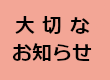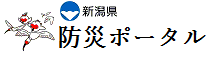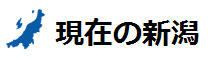本文
令和6年6月定例会(提案理由)
令和6年6月定例会提出議案知事説明要旨
議案についての知事の説明を掲載しています。
6月25日 知事説明要旨
令和6年6月定例県議会の開会に当たり、前議会以降の県政の主な動きと、提案致しております議案の概要をご説明申し上げ、議員各位並びに県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
はじめに、令和6年能登半島地震への対応についてです。
今回の地震では50人の人的被害及び2万棟を超える甚大な住宅被害等が発生いたしました。
県といたしましては、被災した施設の早期復旧・復興はもとより、被災された方々が一日も早く日常生活を取り戻していただけるよう、最大限取り組んでまいりました。
直江津港や両津港などにおいても、大きな被害が発生しましたが、本県の要望を踏まえた、ふ頭への特例的な国の財政措置等の支援を活用しながら、3月には応急工事を全て終え、当面の港湾の利用が行われているところです。
また、新潟市などで発生した液状化現象による甚大な宅地被害に対しましては、先月31日に、国から液状化対策に係る地方単独事業についての特別交付税措置が決定されたことも踏まえ、新たに、被害を受けた宅地の復旧に係る経費について、市町村と連携しながら支援してまいります。
加えて、被災した中小企業者等の施設や設備の被害調査が進む中で、復旧等に係る経費が当初の見込みを上回ることが想定されることから、早期の事業再建に必要な支援を増額するため、関連する補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
また、県内の被災者に対し、全国の皆様から多くの義援金をお寄せいただきました。ここに謹んで感謝の意を表し、心よりお礼申し上げます。いただいた義援金は温かいお気持ちとともに被災市町村へ配分し、市町村から、順次、被災者の方々へお届けするよう進めてまいります。
さらに、今後の防災対策についてでありますが、これまでも大規模災害が発生した際には、その振り返りを行い、必要に応じて県の地域防災計画に反映してまいりました。この度の能登半島地震においても災害対応や防災対策上の主要な優先課題を抽出し、その取組の方向性を検討するため、有識者で構成する検討会を設置し、今月5日に第1回目の検討会を開催しました。検討会では、地震・津波からの避難対策、孤立地域対策、避難所の運営対策など、自然災害における防災対策を中心に課題について検討していただき、その議論の中で、自然災害と原子力災害の複合災害についても併せて検討していただきます。検討会の結果を踏まえ、今後の防災対策の強化に取り組んでまいります。
第二点目は、「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産登録についてです。
今月6日、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスから、「佐渡島(さど)の金山」について、世界遺産登録を考慮するに値する価値があることが認められました。その上で、価値をより明確にすることや、保護措置をより強化するための指摘等がなされ、「情報照会」という勧告となりました。
世界遺産登録の実現に向けては、今年3月、私自身が佐渡市長とともに再度パリを訪問し、委員国の大使等に文化遺産としての価値や地元の熱意を直接伝えるとともに、4月には、駐日大使等を佐渡にお招きし、佐渡の歴史や文化を体験いただくなど、委員国の理解を得られるよう取り組んできたところです。
勧告を受け、先般、国に対し、7月下旬にインドで開催される世界遺産委員会において、登録のコンセンサスを得られるよう政府一丸となり、より一層の尽力をされるよう、要望したところであります。
県といたしましても、このたびの勧告を真摯に受け止め、国や佐渡市と連携し、登録実現に向け全力で取り組んでまいります。
続いて、本県の主要課題について、順次ご説明いたします。
第一点目は、子育てに優しい社会の実現についてです。
令和5年の人口動態における本県の合計特殊出生率は、概数で1.23と過去最少となるなど、現在の少子化は危機的な状況にあり、まさに喫緊の課題として対策を一層強化・推進していく必要があると認識しております。
国においては、少子化対策の強化に向けて、児童手当や育児休業給付を拡充するとともに、財源確保のための「支援金制度」の創設などが盛り込まれた子ども・子育て支援法が今月5日、成立いたしました。
県といたしましては、「妊娠・出産から子育てまでの節目における経済的負担の軽減」「結婚を希望する方への支援」「こどもを生み育てやすい環境の整備」を三つの柱として、結婚から妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援を更に強化・推進し、子育てに優しい社会の実現を目指してまいります。
経済的負担の軽減につきましては、本県独自の取組である「新潟県こむすび定期」について、昨年10月の制度開始以降、年間出生者数が約11,000人のところ、本年5月までの7か月間で約8,000 件の申請があり、順調に活用が進んでいるものと考えております。申請時のアンケートでは「県がしっかりと子育て世代に向き合い、応援してくれていると安心した」、「子育てにはお金もかかるので、とてもありがたい制度だと思う」などの声をいただいており、引き続き、対象者の皆様から確実に申請していただけるよう、市町村等と連携して周知を強化してまいります。
また、今年度、新たに取り組む「にいがた安心こむすび住宅推進事業」については、今月6日から事業者の募集を開始したところであり、説明会には約140社の買取再販事業者の皆様から参加いただきました。秋ごろには、実際に、こどもの事故防止や家族のふれあい等に配慮した、子育てに優しいリノベーション住宅の販売が開始される予定です。今後、事業者等による協議会を設置するなど、本制度の周知・推進に一層努めてまいります。
加えて、マッチングシステムの機能向上による結婚支援や、4月に施行されたこども条例を契機とした社会全体でこどもを大切にし、子育てを支える気運醸成など、各種施策を通じて、子育てに優しい社会の実現に向けて、全力を挙げて取り組んでいるところです。
必要な財源の確保等につきましては、今月6日に、国に対して、地方の創意工夫ある支援を後押しするための継続的な財政支援などについて要望を行ったところであり、引き続き、国と地方が一丸となり、子ども子育て施策の一層の充実・強化に努めてまいります。
第二点目は、脱炭素社会への転換についてです。
昨年度来、住宅の省エネ化に向けて、雪国型ZEH導入支援等を行っているところですが、4月には、有識者、住宅関係団体、金融機関、市町村からなる新潟県雪国型ZEH推進協議会を設立し、関係機関との情報交換や県民への普及啓発に連携して取り組んでいるところです。
あわせて、雪国型ZEHの普及促進に積極的に取り組む事業者を広く県民に紹介する雪国型ZEHビルダー・プランナー登録制度を開始したほか、5月から雪国型ZEH等導入促進補助金の募集を開始したところです。
また、本県において普及の進んでいない家庭用太陽光発電設備及び蓄電池の設置を促進するため、太陽光発電設備等共同購入に関する協定を事業者と締結し、購入希望者の募集を開始しました。多くの皆様から応募いただけるよう市町村とも連携しながら、広報に努めてまいります。
気温上昇や豪雨など、地球温暖化を原因の一つとする気候変動の影響がますます顕在化する中、脱炭素への転換を着実に達成するためには、あらゆる主体が自らの取組を更に加速化する必要があります。県では、脱炭素への転換を推進するための条例の検討に着手したところであり、今後、県民や事業者をはじめ市町村など、様々な方のご意見を伺いながら条例制定に向け取り組んでまいります。
第三点目は、デジタル改革の実行についてです。
医療分野においては、医療アクセスが困難なへき地における診療機会の拡大に向け、モデル事業として、事業に参加する市や町の診療所等において、オンライン診療の実証を行っており、その結果を踏まえ、他地域への展開を図るなど、持続可能な形で広く普及するよう取組を進めてまいります。
また、現在、専門医が少ない診療分野におけるオンライン診療の導入についても検討を進めているところであり、引き続き、県内どこに住んでいても安心して医療が受けられる環境づくりに向けて取り組んでまいります。
次に、行政のDXについては、「デジタル改革の実行方針」に基づき、県民サービス向上のため、県単独で変更できる行政手続について、処理件数ベースで約9割がオンラインで申請・届出できるようになりました。
また、8月末の収入証紙の販売終了や、9月の運転免許関係手続のキャッシュレス決済のスタートにより、県民サービスのデジタル化がより一層進むこととなります。
今後もより県民の利便性が高くなるよう、県民目線での行政サービスの変革を進めてまいります。
第四点目は、県民の安全・安心の確保についてです。
まず、柏崎刈羽原子力発電所についてでありますが、3月21日に再稼働に対する政府方針について、経済産業大臣からの理解要請を受けました。これに対し、私からは、福島第一原発事故に関する3つの検証の取りまとめ、原子力規制委員会の追加検査を踏まえた判断、技術委員会における安全対策等の確認、原子力災害発生時の避難の課題への取組などを材料に議論を進め、県民等の意見を聞き、 その上で判断・結論を出して県民の意思を確認することを考えている旨をお伝えしました。また、今月6日に原子力防災担当大臣及び原子力規制庁長官に対し、13日には経済産業大臣に対して、柏崎刈羽原発の安全対策の徹底や、より実効性のある原子力防災対策の構築等、現時点における課題について、国策として原子力発電を進めてきた国の責任において対応するよう要望してまいりました。 国からは、関係省庁が連携し適切に対応する旨の回答をいただきました。
また、昨年7月に柏崎市長及び刈羽村長と実施した道路の整備等に関する要望に対し、北陸自動車道と接続するスマートインターチェンジや、米山サービスエリアへの緊急進入路等について、地方負担分なく整備できるよう予算を確保するとの回答をいただいたところです。これを踏まえ、緊急進入路整備等の事前調査に関連する補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。
柏崎刈羽原発の安全対策等については、技術委員会において、国に対し確認を行っているところであり、引き続き着実に進めてまいります 。
さらに、本年11月に適用期間が終了する核燃料税については、原発が停止している状態であっても安全・防災対策など、一定の財政需要が存在しており、税収をさらに確保する必要があることから、出力割の税率を引き上げ、価額割と出力割の合計税率を17%相当から18%相当にすることとし、関連する条例案を本定例会にお諮りしているところです。
次に、地域医療の確保についてです。
持続的な医療提供を支えるためには、その基盤となる医療人材の確保が不可欠です。
このため、養成段階からの医師確保に向け、定着率が高い医学部地域枠の新設・拡大を行い、令和6年度は前年度より7名増となる12大学77名としたところです。
また、臨床研修医の確保に向けて、臨床研修病院における魅力向上や研修環境整備に尽力いただいたことに加え、県独自の研修コースや市町村と連携した海外留学支援、県外の人気病院と連携した研修プログラムの拡大などに取り組んだ結果、令和6年度の臨床研修医数は、過去最高の161名となり、これまで最多の昨年度を14名上回ることができました。
引き続き、医師不足解消に向けて、さらなる医師確保に全力で取り組んでまいります。
県央圏域においては、去る3月1日に済生会新潟県央基幹病院が開院するとともに、4月1日に県立加茂病院、吉田病院が指定管理者制度に移行し、医療再編による新たな医療提供体制がスタートいたしました。
県央基幹病院については、現在、多くの外来・入院患者の診療を行っていることに加え、救急搬送についても、目標としている年間受入数に到達するペースで受入れを行っているところです。病院の使命である「断らない救急」や、「地域がひとつの病院」の実現に向け、引き続き、圏域内の医療機関などと連携・協力しながら、住民が安心して医療を受けられる体制の構築に努めてまいります。
また、上越医療圏においては、3月の上越地域医療構想調整会議で、圏域全体の抜本的な医療再編について、中核病院の集約による機能強化や、身近な病院の機能・規模の適正化、地域全体での医療人材の確保・活用などをパッケージで実現するとした大枠の方向性が合意されたところです。4月以降、説明会など様々な機会で地域の皆様への丁寧な説明や情報発信に取り組むとともに、再編案について、地域の関係者と検討を進めているところであり、早期のとりまとめに向け、引き続き、丁寧かつスピード感をもって取組を進めてまいります。
県立病院については、約23億円の赤字となる令和5年度決算を、先月30日に公表いたしました。また、今年度当初予算においても約43億円の赤字を見込んでおり、このままでは令和7年度末にも内部留保資金が枯渇するおそれのある危機的な状況と認識しております。
このため、今年度新たに「県立病院経営改革推進チーム」を設置し、経営力の強化や新たな加算等による収益の増加などの緊急的対策について、既に取組を進めているところです。さらに、人口減少に伴う今後の医療需要の変化や医療従事者の減少などにも対応し、病院事業を持続可能なものとするため、医療再編等の動向と連動しつつ、地域の中での県立病院の役割を見直すなど、抜本的な改革についても検討し、関係者としっかりと議論をしながら進めてまいります。
第五点目は、地域の産業を支える多様な人材の確保についてです。
全国と同様に、本県においても人手不足は喫緊の課題であり、女性や高齢者、障害者など幅広い人材の活用に加えて、事業者ニーズを踏まえながら外国人の受入れ拡大にも取り組んでいく必要があると考えております。
県では「外国人材受入サポートセンター」を設置し、県内企業からの相談に対応するとともに、留学生を対象とした企業説明会を開催するなど、外国人が活躍できる環境整備に努めているところです。
また、私自身、8月には「交流協力に関する覚書」を締結したベトナム、ビンロン省・タインホア省を訪問し、現地企業とのビジネスマッチングをはじめ、省政府との連携により、現地の高度人材や働く意欲のある方々と受入れを希望する県内企業との人材マッチングに取り組んでまいります。
第六点目は、交通ネットワークと交流人口の拡大についてです。
令和5年度の新潟空港利用者数は、令和元年度以来、4年ぶりに100万人を超え、105万6千人となりました。
国内線は、地域航空会社トキエアによる1月の「新潟=丘珠線」就航、4月の「新潟=仙台線」の就航などもあり、利用者数が回復しておりますが、国際線はすべての定期路線が再開されたものの、便数が未だ戻り切っていないこともあり、利用者数は回復途上にあります。
国際線の維持・拡大のためには、イン・アウト双方の利用促進が重要です。そのため、若年層向けのパスポート取得支援等のアウトバウンド対策に取り組むとともに、引き続き航空会社と連携しインバウンドの獲得に努め、路線の活性化・増便につなげてまいります。
次に、鉄道ネットワークについてです。
新潟地域と上越地域間の在来線の高速化によりスムーズな移動を可能にすることは、県内の社会経済活動の活性化や日本海国土軸の形成の観点から重要であり、3月の検討委員会において、4つのルート案の事業費や時間短縮効果等について報告されたところです。
今年度は、さらに需要予測や費用便益比等を調査するとともに、県民に広く関心を持っていただくための機運醸成や、国に対して事業化に向けた働きかけを行ってまいります。
また、米坂線については、この8月で被災から丸2年となります。先月29日には、関係者による米坂線復旧検討会議が開催され、JR東日本からこれまでの事例を踏まえた4つの復旧パターンが示されました。
県としては、JRによる鉄道復旧・維持が望ましいと考えており、国に対して事業者による早期復旧を促すための環境整備などを要望してまいりました。引き続き、鉄道の持つ災害時のリダンダンシー機能や全国的なネットワークのあり方などの観点も踏まえつつ、地元の意向をしっかりと受け止め、山形県側とも連携しながら、復旧への道筋が得られるよう、調整を進めてまいります。
次に地域の移動手段の確保についてです。
国において、自家用有償旅客運送の制度改善や、タクシー事業者による一般ドライバーを活用した自家用車活用事業の運用が4月から開始され、県内においてもこうした制度を活用した取組の検討が進んでおります。
また、国で検討が進められているタクシー事業者以外の者が実施するライドシェアに関しては、4月に就任した全国知事会の国土交通・観光常任委員長として、安全性の確保を大前提に、地域の実情を反映できる制度とするなどの緊急要望を今月13日に行ったところであり、引き続き、各都道府県とも連携しつつ政府に働きかけてまいります。
県といたしましては、市町村や関係事業者等と連携し、地域のあらゆる交通資源をフル活用した取組を行い、持続可能な移動手段の確保を図ってまいります。
次に、「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」についてです。
飲食店、イベントスペース及び移住相談窓口は、5月末から順次オープンしたところですが、物販スペースを含めた全館については、8月8日にグランドオープンいたします。
インバウンドをはじめ、数多くの来訪が期待される銀座を拠点として、新潟とのヒト、モノ、情報の流れが創出できるよう、多様で豊富な商品を背景にあるストーリーと併せて伝えるとともに、訴求力の高いイベントを開催するなど、本県の魅力を積極的に発信してまいります。
第七点目は、付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現についてです。
昨年は、梅雨明け以降、過去に例のない異常高温と少雨が続き、米の1等級比率の大幅な低下、果実の肥大不良、稲や野菜の枯死など、県内各地で農作物等に大きな被害が発生しました。
今夏についても、昨年のような高温・渇水を心配する声が聞かれる中、県といたしましては、昨年度、外部有識者等で構成する研究会からいただいた提言を踏まえ、異常高温による被害を軽減するための技術対策の確実な実践や、異常気象に対応した品種転換等の取組をサポートし、農業者の所得確保と経営安定に努めてまいります。
また、生産現場において、より迅速な技術対策が講じられるよう、生産者が稲の生育データをクラウド上でリアルタイムに把握できるシステムを、本年度、新たに構築しているところです。
加えて、高温耐性を持つ米の極早生品種の現地実証や、高温耐性コシヒカリBLの早期開発等に取り組み、異常気象下においても食味や品質に優れた新潟米の安定供給を目指してまいります。
次に、県産農林水産物のブランド化についてです。
先般、県推進ブランド品目の一つである「のどぐろ」について、新潟県産の高規格のどぐろを「新潟のどぐろ 美宝(びほう)」と名付け、新ブランドとして発表するお披露目イベントを、東京都内で開催いたしました。
こうした品目ごとの特長を活かしたプロモーションを積極的に展開するとともに、県産農林水産物の品質の高さ、生産者の実直さを「うまいに、まっすぐ。新潟県」と表現したキャッチコピーとロゴマークを公表したところであり、これらを広く活用し、生産者をはじめ観光・飲食業等の関係者とも連携しながら、産地「新潟」のブランドイメージの向上に取り組んでまいります。
第八点目は、行財政運営についてです。
先般、新潟県行財政基本方針に基づく堅実な行財政運営を進めていくため、外部有識者による新潟県行財政アドバイザーを設置し、本県の行財政運営について専門的・客観的な観点から意見及び助言をいただく体制を構築したところです。
県といたしましては、基本方針の下、引き続き堅実に収支を見通しながら、持続可能な財政運営の実現に向けて取り組んでまいります。
また、県債管理基金の公債費調整分を活用した公債費の償還の前倒しについては、マイナス金利解除後初めて示される内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」における金利推計等に基づく基金残高の見通しを踏まえながら、まずは本年8月から始めてまいります。
第九点目は、県の最上位計画である総合計画の改定についてです。
4月に各界の有識者による「総合計画評価・策定検討委員会」を設置し、今年度で計画期間が終了する総合計画の改定に向け検討を開始いたしました。
現在、委員の皆様から総合計画に掲げた目標に対する各政策の進捗状況や県の取組などについて、評価をいただくとともに、多岐にわたるご意見をいただいております。
今後、こうした委員会の評価や意見を踏まえつつ、議会においてご議論いただくとともに、市町村からご意見を拝聴するなどした上で、年度内の改定に向け検討を進めてまいります。
最後に、北朝鮮による拉致問題についてです。
曽我ひとみさんら5人の帰国から21年が経過しましたが、拉致被害者やそのご家族の高齢化が進む中、いまだ具体的な進展は見られず、もはや一刻の猶予も許されません。
4月に駐日韓国大使にお会いした際には、拉致問題解決に向けた協力をお願いし、大使からは、今後も両国がしっかり協力していくべきとの心強い言葉をいただきました。
また、5月に開催された国民大集会で岸田総理大臣からは、「日朝首脳会談の実現に向け、働きかけを一層強めていく」との意欲が改めて示されました。
政府には、全ての拉致被害者の帰国に向け、全力で外交交渉に取り組んでいただきたいと考えております。
県としても国に対し、拉致問題の早期解決を求めるとともに、県民に拉致問題への関心を持ち続けていただき、一層の世論喚起を進めていくため、政府の交渉等の動きに関する情報提供を改めてお願いしたところです。
政府の取組を後押しするため、引き続き、市町村長の会等とも連携し、県民集会、県内各地でのパネル展や映画上映会など、幅広い世代に向けた啓発活動に取り組んでまいります。
続いて、提案しております主な議案についてご説明申し上げます。
第94号議案は、一般会計補正予算案でありまして、総額17億7,980万9千円の増額補正についてお諮りいたしました。
今回の補正は、先ほども申し上げたとおり、令和6年能登半島地震からの迅速な復旧・復興を図るとともに、柏崎刈羽原子力発電所地域の住民の安全と安心を確保するために必要な経費を計上したところです。
その結果、補正後の予算規模は、1兆2,889億2,980万9千円となります。
次に、その他の主な条例案件等についてご説明申し上げます。
第97号議案は、児童福祉法の改正に伴い、児童発達支援の類型の一元化に対応するため、第99号議案は、新潟県少年自然の家について、指定管理者による管理を可能とするため、それぞれ、条例の所要の改正を行うものです。
次に、第100号から第102号までの各議案は、緊急を要するため、やむを得ず専決処分を行ったものについて、承認を求めるものであります。
すなわち、第100号議案、第101号議案、第102号議案はそれぞれ、令和5年度一般会計補正予算、令和5年度災害救助事業特別会計補正予算、令和5年度新潟県港湾整備事業特別会計補正予算であり、歳入予算及び歳出予算ともに最終見込額又は確定額を計上したものであります。
最後に、第103号議案は、警察署確認事務委託において、契約相手方に契約解除条項に該当する事案が確認されたため、損害賠償請求に係る訴えを提起するものであります。
以上、主な議案の概要につきまして、ご説明申し上げましたが、何とぞ慎重にご審議のうえ、各議案それぞれについて、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
7月1日 知事説明要旨
ただいま上程されました第1号諮問及び第2号諮問は、漁港設備使用料未納に係る処分の取消しを求める審査請求の決定に当たって、諮問するものであります。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
7月16日 知事説明要旨
ただいま上程されました議案5件は、いずれも人事に関する案件であります。
第104号議案は、副知事を選任するため、第105号議案は、監査委員を選任するため、第106号議案は、公安委員会委員を任命するため、第107号議案は、収用委員会委員を任命するため、第108号議案は、土地利用審査会委員を任命するため、それぞれお諮りいたしました。
よろしくご審議のうえ同意を賜りますようお願い申し上げます。
令和6年6月定例会・議会情報項目一覧へ
新潟県議会インターネット中継のページへ<外部リンク>
新潟県議会のトップページへ