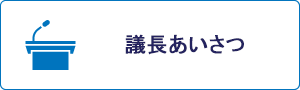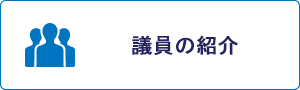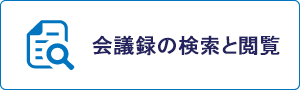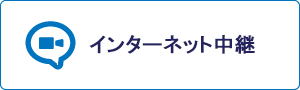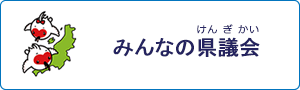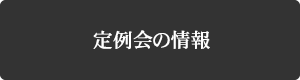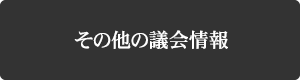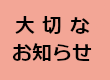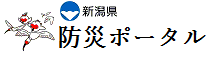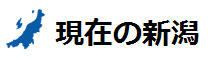本文
令和7年2月定例会(請願第1号)
第1号 令和7年2月7日受理 厚生環境委員会 付託
年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める意見書提出に関する請願
請願者 全日本年金者組合新潟県本部 執行委員長 稲葉正美
紹介議員 馬場秀幸君
(要旨)いま年金受給者は、物価高騰のもとで厳しい生活を強いられている。物価上昇を反映しない年金額改定ルールにより2013年度からの12年間で物価は11.3%上昇したが、年金額は3.5%しか上がらず、7.8%も実質的価値が目減りした。追い打ちをかけるようにこの4月からの年金額改定でも、物価上昇率が2.7%であるにもかかわらず賃金スライド率2.3%が適用されて0.4%低くされた上、さらにマクロ経済スライドを適用した調整率0.4%を減じた1.9%の改定率で、合わせて0.8%も減額される。このため、新潟県内の給付減は81億円(共済年金を除く)にも及ぶ。高齢者に支給される年金は、その殆どが消費に回る。年金減額による購買力の衰退が地域経済に大きな影響を与えている。年金だけでは生活できず、老骨に鞭打って仕事に就く高齢者が全国で912万人と過去最多になり、生活保護世帯の55.1%の90万5000世帯が高齢者世帯で年々増える傾向にあると報じられている。
2024年7月3日、厚生労働省から「財政検証」結果が公表され、「過去30年投影」ケースの場合の課題が公表された。
(1) 2057年度には、モデル世帯の所得代替率は2割低下し、基礎年金は3割低下する。
(2) マクロ経済スライドの調整期間終了年度は、厚生年金は2026年度だが、国民年金(基礎年金)は2057年度まで減額が続く。
(3) 年金積立金残高は、計画より70兆円積み増した290兆円(2024年3月末)で、うち、配当・利子収入は約50兆5500億円である。
新潟日報は、7月6日付社説「安心できる制度に改革を」で、「年金の給付水準は、給付を自動的に抑制する『マクロ経済スライド』などの影響で、年齢を重ねるごとに低下する。現在満額で月6万8000円の国民年金(基礎年金)は、33年後の2057年度に水準が3割低下する。国民年金のみで暮らす人には打撃が大きい。低年金でも安心できるような対策を急いで講じる必要がある。」と報じ、警鐘を鳴らしている。基礎年金の給付水準が低下し続けることは、今でも生活保護基準以下の生活を強いられている低年金の受給者にとっては耐え難い生活が続く。
年金受給者は何よりも「生活できる公的年金」を願っている。厚生労働省は、基礎年金の長期間の給付抑制による給付水準の低下に歯止めをかけるため、厚生年金の積立金を活用した財政調整により、厚生年金と国民年金(基礎年金)のマクロ経済スライドの調整期間を2036年度で同時に終了させることを検討していたが、厚生年金の受給水準が一時的に目減りすることや「国庫負担が増える」などの理由から2029年度の次期「財政検証」まで先送りされると報じられている。しかし、今後も両年金の調整期間が続き、その間給付水準も低下し続けることは、物価高騰に苦しむ年金受給者に追い打ちをかけるものになりかねない。
「財政検証」報告では、この10年間は年金積立金から両年金勘定への給付費としての繰り入れは殆どない。今後、基礎年金勘定の給付費(2021年価格=11兆3000億円)の調整率による累計額は、直近の20年間でも約7兆円で、配当・利子収入積立金のわずか13.8%に過ぎない。急激な株価変動を招くこともなく、全ての年金受給者に共通する基礎年金の調整期間を厚生年金の調整期間終了と同時に終了し、基礎年金を底上げすることは十分可能である。また、国庫負担分も一挙に増えるのではなく、年々徐々に増えるので財政計画通りに行く。
国民年金法第75条は積立金の運用について「将来にわたって、国民年金事業の運営に資することを目的として行うものとする。」と定めている。法の趣旨に則り、積立金を活用して基礎年金の調整期間を厚生年金の調整期間終了と同時に終了して、基礎年金の底上げ実現を図ることを強く願うものである。
ついては、貴議会において、地方自治法99条に基づいて、年金積立金を活用して早期に基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間を終了し、給付水準を引き上げることを求める意見書を内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、厚生労働大臣に提出されたい。