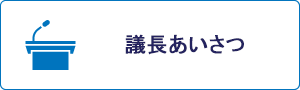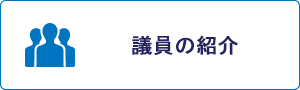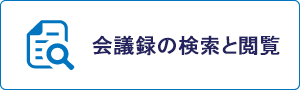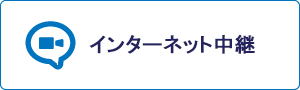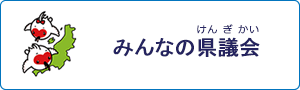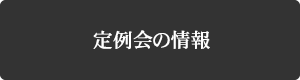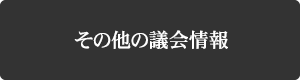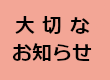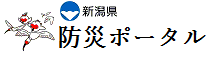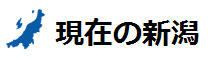本文
令和7年2月定例会(提案理由)
令和7年2月定例会提出議案知事説明要旨
議案についての知事の説明を掲載しています。
2月17日 知事説明要旨
令和7年2月定例県議会の開会に当たり、私の所信の表明と提案いたしております議案の概要を申し述べ、議員各位並びに県民の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと存じます。
はじめに、昨年4月より改定作業を進めてまいりました総合計画についてです。
総合計画につきましては、11月に計画の見直し素案を公表し、12月定例県議会でのご議論はもとより、市町村やパブリックコメントで県民の皆様から寄せられたご意見等を踏まえながら、必要な修正を加えた上で、先般、改定案としてとりまとめ、公表いたしました。
改定案では、「住んでよし、訪れてよしの新潟県」を基本理念に掲げ、県民の皆様が、新潟に住んでいることを誇りに思い、これからも住み続けたいと思える、そして、国内外の方々が新潟に魅力を感じ、訪ねてきていただける新潟県の実現に向けて、県民最優先の基本姿勢の下、全力で取り組んでまいります。
また、総合計画の人口ビジョンでお示ししたとおり、今後も不可避的に人口の減少局面が継続する中、将来的な「人口定常化」を目指し、少ない人口であっても、成長力のある持続可能な社会を構築していく必要があります。
このため、本定例会にお諮りしている新年度予算案においては、この計画案でお示しした分野横断的に対応すべき6つの重要課題にそった政策パッケージを基本に「住んでよし、訪れてよしの新潟県」づくりの新たな一歩を踏み出す予算として編成したところです。
以下、本県の主要課題について、順次述べさせていただきます。
第一点目は、子育てに優しい社会の実現についてでありますが、大手シンクタンクが厚生労働省の統計データをもとに推計した昨年1年間の出生数は、全国で68万5千人で前年から4万人減少し、これまでで最も少なくなる見通しとなり、合計特殊出生率も1.15程度を割り込む見通しとなるなど、少子化に歯止めがかからない状況にあります。
県としましては、「妊娠・出産から子育てまでの節目における経済的負担の軽減」「結婚を希望する方への支援」「こどもを生み育てやすい環境の整備」を三つの柱として、結婚から妊娠・出産・子育てまでライフステージに合わせた切れ目のない支援を市町村や民間団体とも連携しながら強化してまいります。
まず、経済的負担の軽減につきましては、こどもの入園、入学の節目において、子育て世帯への経済的支援を金融機関と連携して行う「新潟県こむすび定期」事業や、子育て世帯等の住宅購入を支援する「にいがた安心こむすび住宅推進事業」に引き続き取り組んでまいります。
また、経済的負担の軽減とともに、こどもを生み育てやすい環境の整備に資する取組として、新たに、いわゆる「小1の壁」に直面し、悩みや不安を抱える共働き家庭等を支援するため、市町村が実情に応じて放課後児童クラブ等のサービスを充実できるよう自由度の高い交付金により支援してまいります。
結婚を希望する方への支援として、これまでの出会いの場の創出支援に加え、行動に移せていない層や若年層への支援を強化するため、新たに、同窓会など若者が気軽に出会える場を創出する市町村を支援するとともに、若年層への早期アプローチとして、新たに大学生など、より多くの若者にライフデザインを考える機会を提供してまいります。
加えてマッチングアプリの安全・安心な利用や県の支援策など結婚に関する有益な情報を様々な手法で発信するなど、新たな取組も進めてまいります。
本県の少子化の遠因となる若者や女性の流出が続く中、若者や女性が活躍できる地域づくりを推進し、東京圏等の若者や子育て世帯の更なる呼び込みなど、本県への人の流れの創出・拡大を図ることも重要です。
このため、県内企業の多様で柔軟な働き方や女性活躍の更なる取組の促進に向けて、現行のハッピー・パートナー企業登録制度を見直し、新たな企業認定制度を創設するとともに、認定企業に対して、女性が働きやすく、魅力ある職場づくりの取組を新たに支援してまいります。
また、県内企業や大学等で構成する民間団体と連携し、学生・県内企業・県内大学の交流拠点の開設を支援するとともに、企業ニーズを踏まえたマッチングイベントを実施するなど、学生が参加しやすい多様な形での産学連携を通じて、大学の魅力向上を図り、学生が県内企業と直接つながる機会を創出してまいります。
加えて、連携協定先の企業と連携し、デジタルデータを活用して本県への潜在的な移住関心層に向けた戦略的な広報を展開するとともに、「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」の相談窓口における取組の充実や、国が拡充予定の移住者への支援制度の活用により、東京圏からのU・Iターンを促進してまいります。
第二点目は、持続可能で暮らしやすい地域社会の構築についてです。
まず、地域医療体制の構築についてでありますが、人口構造の変化に伴い、高度・専門的な医療を必要とする患者が減少していることや、昨今の物価高騰による医薬品費や診療材料費の上昇、人件費の増加などが重なり、診療報酬という公定価格によって事業を行う医療機関は、総じて厳しい経営環境に置かれているものと認識しております。
本県においては、地域医療の2大ネットワークである県立病院と厚生連がともに危機的な経営状況に直面しており、県としても大きな危機感を持っているところです。
厚生連では、厳しい経営状況からの脱却を目指し、まずは最大限の努力により、緊急的な経営改善の取組を徹底して進めているところと承知しておりますが、持続可能な安定経営を実現するには、依然道半ばの状況にあると考えております。
そのため、県としても、地域の医療提供に支障が生じないよう、国の経済対策も最大限活用しながら、厚生連の事業継続に向けた経営改革に対する財政支援を含め、県内医療機関の足元の経営基盤を支えるための緊急的な支援に取り組んでまいります。
しかしながら、今後も人口減少が続き、医療従事者の確保が更に困難になることが見込まれるなど、社会環境が大きく変化していく中で、安定して医療を提供し続けるためには、個々の病院単独での機能・規模の見直しだけではなく、圏域全体を見据えて、最適な役割分担と機能分化を推進していくことが一層重要になったものと受け止めております。
県といたしましては、各圏域における医療提供体制の確保の観点から、厚生連をはじめとする各病院の経営改革やあり方の見直しなどの動きを後押ししながら、圏域ごとの医療再編の議論につなげ、将来にわたり持続可能な医療提供体制を構築してまいります。
持続的な医療提供を支えるためには、その基盤となる医療人材の確保が不可欠です。
このため、養成段階からの医師確保に向け、県外の大学や市町村等と連携し、新年度の医学部地域枠を、今年度より2名多い79名に拡大したところです。
また、臨床研修医確保の取組を強化しつつ、着実に増加している臨床研修医の本県での専攻医としての定着を促進するため、新たに二次医療圏単位での専門研修プログラムの構築を支援するなど、医師確保に全力で取り組んでまいります。
次に、公共交通ネットワークの維持・充実についてです。
本県の地域公共交通は、人口減少や運転手不足などを背景に、バス路線の減便・廃止やタクシー事業者数が減少するなど、地域における移動手段の確保が喫緊の課題となっています。
こうした交通空白の解消に向けた有効な方策である、日本版ライドシェアの取組については、新潟市南区や小千谷市で実施されており、さらに妙高市や湯沢町でも導入が予定されているなど、着実に広がってきております。
県といたしましては、地域の実情に応じた移動手段を確保するため、こうしたライドシェア導入の取組を支援するとともに、市町村や関係事業者等と連携し、地域の交通資源をフル活用した取組をさらに進めてまいります。
新潟地域と上越地域を結ぶ幹線交通のアクセス改善に向けては、地元での利用拡大を図ることが重要です。
そのため、特急しらゆきや高速バスの運賃等の割引きや旅行商品の造成を支援するとともに、地元企業等による利用を促進してまいります。
また、今年8月で被災から3年を迎える米坂線については、現在、鉄道としての復旧を目指しつつ、JR東日本から示された4つの復旧パターンにおける自治体の負担等について、協議を進めているところです。できるだけ早く復旧への道筋が得られるよう、地元の意向をしっかりと受け止め、山形県とも連携しながら、JRと調整を進めてまいります。
次に、地域の暮らしと経済活動の維持・発展についてです。
まず、地域の魅力を活かした交流人口の創出については、新たに棚田日本一の魅力を活かし、多様な主体が参画するフォーラムを設置し、今後の事業展開の検討を進めるとともに気運醸成を図ってまいります。
また、地域の経済活動を支える物流の維持・確保に向けては、運転手不足が続く中、物流の効率化が求められていることから、荷主や物流事業者の連携を促進するとともに、複数事業者による中継運送や共同配送などの取組を新たに支援してまいります。
人手不足が喫緊の課題となる中、本県が外国人材に選ばれ、定着してもらうためには、安心して働ける環境整備が重要です。
このため、新たに、県内企業が行う就労環境の整備や日本語教育を支援するなど、企業のニーズを踏まえた施策を展開してまいります。
次に、将来の夢や希望を育みかなえる教育の推進についてです。
次期「県立高校の将来構想」については、生徒・保護者アンケートやパブリックコメントを通じて、県民の皆様のご意見を伺いながら策定を進めてきたところであり、これらのご意見や本定例会における議論を踏まえ、今年度末に公表することとしております。
今後、より一層少子化が進行する中にあっても、本県高校教育の質の維持・向上を図ることが重要であり、新年度においては、将来構想を具現化するため、教育庁内に「将来構想推進室」を設置し、学校・学科の再編整備を推進するとともに、多様化する教育ニーズに対応した、生徒・保護者から選ばれる魅力ある学校づくりに取り組んでまいります。
近年、不登校のこどもが増加傾向にあることは喫緊の課題と認識しております。これまでの小中学校を中心とした対策をさらに充実させるとともに、小学校入学前から高校卒業までの、切れ目のない不登校対策に取り組んでまいります。
また、教員がこどもたちと向き合うことのできる環境を作るため、教員を補助する外部人材の活用をさらに拡充するなど、教員の業務支援を進めることで、多忙化解消に取り組むとともに、新たに、本県の特色ある教育活動など、本県教員として働くことの魅力を戦略的に発信することにより、教員の確保を図ってまいります。
第三点目は、高い付加価値を創出する産業構造への転換についてです。
本県経済は、持ち直しつつあるものの、エネルギー・原材料価格の高騰などにより、物価高が長期化しており、個人消費の一部に弱い動きがみられるほか、先行きに不透明感を持つ企業もあるなど、依然として厳しい状況にあるものと認識しております。
このため、国の交付金等を活用し、県内中小企業者等の事業継続に向けたコスト増加に対応するための支援や、市場環境の変化に対応した新分野展開、地域経済の活性化に向けた取組等を支援してまいります。
また、賃上げに対する国の助成金や税制などの活用を促すとともに、DX・生産性向上による収益改善や、適切な価格転嫁の促進による持続的な賃上げに向けた環境整備を進め、引き続き関係団体等と連携しながら地域経済の好循環の実現に向けて取り組んでまいります。
次に、起業・創業の支援についてでありますが、今後、将来の県経済をけん引するスタートアップの成長を加速させるためには、事業拡大のために必要となる資金や、経営者をサポートする人材の確保などが必要です。
このため、新たに、ベンチャーキャピタルや外部経営人材とのマッチングなどにより、成長に必要となる経営資源を首都圏から呼び込み、県内においてもスタートアップが活躍できる環境を構築してまいります。
県内産業の高付加価値化のためには、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上など、県内企業のデジタル化を一層促進させることも重要です。
このため、金融機関等と連携した意識啓発や相談に対応するとともに、新たに、経済産業省の「DX認定」の取得を目指す企業への伴走支援を行うなど、企業のデジタル化の取組状況に応じたサポートを展開してまいります。
次に、防災産業クラスターについてです。
本年9月に、国が主催する「ぼうさいこくたい」が本県で開催され、防災関連企業や防災活動に取り組む団体など、県内外から多くの来場が見込まれることから、防災に関する新たなニーズを掘り起こし、産業振興にもつなげたいと考えております。
そのため、県では、産学官連携のプラットフォームである「にいがた防災ステーション」と連携した展示商談会を開催し、新潟発の防災関連商品の認知度向上や、新たな販路開拓に取り組んでまいります。
本県は、アニメに関する教育機関や制作会社数が全国でもトップクラスとなっているほか、複数の関連イベントが開催されるなど、アニメを中心としたメディア芸術の拠点として優位性を有しています。
この優位性を活かし、アニメで「選ばれる新潟」になるため、クリエイターが新潟で創作活動を行い、世界で活躍できる環境づくりが進むよう、市町村や教育機関、関連事業者等が参画する推進体制を構築し、メディア芸術に関する調査・分析等に基づき今後の戦略を検討するとともに、シンポジウム等を開催し気運醸成を図ってまいります。
次に、付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現についてです。
気候変動や国際情勢の不安定化等により、食料安全保障上の懸念が一段と高まる中、本県が、新潟米の安定生産と供給を通じて食料安全保障に貢献し続けるためには、水田農業で儲かる農業経営を実現し、次代の地域農業の担い手にしっかりと引き継いでいくことが重要です。
このため、主食用米と非主食用米を合わせた水田所得の最大化を目指し、新たに、県内食品産業等からの需要も高い非主食用米を、超省力・低コストで生産し、かつ多収穫が可能な生産モデルの実証に取り組んでまいります。
また、需要の変化に対応できる競争力と魅力のある園芸産地を育成するため、今年度中に策定する次期園芸振興基本戦略に基づき、本県の園芸を牽引する販売額1億円を超える経営体を増やしていくとともに、産地による高度先端技術の導入や企業との連携等の取組を支援することにより、園芸産地の構造改革を進めてまいります。
加えて、県産農林水産物の魅力を県内外で発信し、「うまいに、まっすぐ。新潟県」のイメージの定着と多様な販路の開拓に取り組んでまいります。また、新たなブランドとなり得る新品種の開発やフードテックによる製品開発等、中長期的な視点を持って、戦略的に試験研究を進めるほか、農山漁村の豊かな地域資源を活用し、にぎわいや雇用を創出する事業活動を促進するなど、本県農林水産業の付加価値を高め、地域に人や投資を呼び込むための施策を展開してまいります。
第四点目は、国際拠点化と戦略的な海外展開・交流促進についてです。
まず、「佐渡島(さど)の金山」を核とした交流拡大についてでありますが、世界遺産登録を契機とした観光需要をさらに取り込むため、国内外に向け、観光プロモーションを強化するほか、富裕層をターゲットとしたクルーズ船のプレミアムモデルツアーの造成も進め、世界遺産のブランド力を最大限活用しながら、市町村や観光関係者と連携して本県への誘客拡大と周遊促進を図ってまいります。
また、世界遺産を構成する資産の適切な保存を支援するとともに、多様な年代を対象とした、担い手確保のための学習・体験プログラムを新たに実施し、「佐渡島(さど)の金山」の普遍的価値を将来にわたって継承してまいります。
加えて、島内道路の安全性・利便性の向上に取り組み、増加が見込まれる観光客の円滑な移動環境の整備に努めてまいります。
次に、アジア成長市場を核とした交流拡大についてです。
初のチャーター便が新潟から就航し今年で35周年を迎えるモンゴルとの交流拡大に向け、留学生交流等の促進に対する支援や、モンゴル国立大学との学術協力協定を契機とした県立大学モンゴルリエゾンオフィス開設による大学間交流の促進に取り組んでまいります。
また、ベトナムとの交流につきましては、ビンロン省やタインホア省との人材交流等を一層促進するため、現地学生と県内企業とのオンラインでの人材マッチングや、多文化共生に向けたベトナムからの就労者や学生等との交流イベント等を行ってまいります。
次に、大阪・関西万博についてです。
国際的イベントである大阪・関西万博は、4月の開幕に向け準備が着実に進んでおりますが、本県といたしましても各種メディアやアンテナショップを活用したプロモーションや関連イベントを行うなど、会期前も含め、万博を通じて本県の魅力を国内外にPRしてまいります。
また、会期中は、県の石であるヒスイを通期で展示するほか、本県の食の魅力の発信や、デジタル技術を活用した錦鯉や花火等の県産品を展示するなど、県内各地の多様な地域資源を来場者に発信し、本県の認知度を高めてまいります。
こうした取組に加え、万博の発信力を活用し、展示に関連する海外向けの高付加価値旅行商品や、スキーツアー等を販売することで、県全体への実誘客を図り、交流人口の拡大につなげてまいります。
次に、日本海側の国際拠点化についてです。
今年度の新潟空港利用者数は、国際線の全路線が運航していることなどから、昨年度の105万6千人を上回る見込みとなっております。
これまで空港利用者の増加に向けて、インバウンド・アウトバウンド双方の利用促進を図りながら、路線ネットワークの拡充や利便性向上に取り組んできておりますが、更なる新潟空港の拠点化を図るため、民間事業者の創意工夫を取り入れるコンセッションの導入に向けた取組を進めてまいります。
また、「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産登録や上越地域の大型リゾート開発等のインバウンド需要の増加が見込まれる中、県内公共交通機関のキャッシュレス決済の導入を支援してまいります。
第五点目は、脱炭素社会への転換についてです。
気候変動が本県にもたらす影響が顕在化する中、脱炭素社会の実現に関する基本理念や県、県民及び事業者の責務等を定めた「新潟県脱炭素社会の実現に関する条例」を制定し、取組をさらに進めてまいります。
雪国型ZEHについては、産官学連携による推進協議会を通じて情報交換や普及啓発等を進め、さらなる導入支援に取り組んでまいります。
また、新たに、本県のような豪雪地帯における活用が期待される、軽量かつ柔軟で窓や壁に取り付け可能な次世代型太陽電池の開発に向け、県内における実証試験を支援してまいります。
県内港湾のカーボンニュートラルポート形成については、新潟港及び直江津港において港湾脱炭素化推進計画を策定したところであり、民間事業者による更なる脱炭素化の取組を支援するとともに、県内港を利用したモーダルシフトを行う民間事業者への支援を通じ、物流によるCO2排出量の削減に取り組んでまいります。
さらに産業部門、業務部門の脱炭素化の推進に向けて、新たに中小企業版SBT認定取得を支援するとともに、その取組事例等を広く発信し、県内事業者の脱炭素経営への転換を促進してまいります。
森林吸収源対策については、CO2吸収能力が低下した森林の若返りを図るため主伐・再造林を進めていく必要があります。
このため、森林組合等の経営基盤強化や、デジタル技術を活用した森林管理等による施業地の大規模化を促進するとともに、県内における新たな木材加工・流通体制の整備への支援など県産材需要の創出に取り組むことで、循環型林業を推進してまいります。
第六点目は、デジタル改革の実行についてです。
まず、医療分野においては、モデル事業で得られた知見をまとめた導入ガイドを活用し、へき地におけるオンライン診療の普及を図るとともに、医師が少ない専門分野や休日夜間診療におけるオンライン診療の活用にも取り組むなど、県内どこに住んでいても安心して医療が受けられる環境づくりに取り組んでまいります。
防犯分野においては、県民の自主的な防犯行動を促すため、新たに地域の犯罪発生情報や具体的な防犯対策等の情報を提供する防犯アプリを開発します。
教育分野においては、新たな「県立高校の将来構想」に基づき、遠隔教育の全県的な展開に向けて、配信教員の指導力向上に努めるとともに、令和8年度の「遠隔教育配信センター」の開設に向けて取り組んでまいります。
農業分野においては、農業者の高齢化や労働力不足が進む中、スマート農業技術の活用により、農業の生産性向上と収益性の高い経営を実現していくことが必要です。
このため、スマート農業に関する先進的な知見や技術を有する企業や大学と農業者等が連携した、新たな課題解決プロジェクトの創出を支援してまいります。
行政分野においては、行政手続のオンライン申請の利便性を高めるため、県の行政手続を網羅したポータルサイトを構築し、県民・事業者に対する行政サービスの一層の向上に取り組んでまいります。
第七点目は、公民協働プロジェクトの推進についてです。
本県が抱える課題への対応や、さらなる魅力づくりについて、公と民が率直に議論し、知恵を出し合って具体的な行動に結び付けていくため、令和元年に「公民協働プロジェクト検討プラットフォーム」を立ち上げ、現在、様々な取組が進んでいるところです。
まず、県立都市公園における利用者の利便性向上と公園の魅力向上を目指すPark-PFI制度については、現在実施している鳥屋野潟公園等を対象としたサウンディング調査の結果を踏まえ、導入が可能と判断された公園について、新年度には事業者の公募を実施してまいります。
また、官民が連携して維持管理等の一体的なマネジメントを行うウォーターPPPについても、流域下水道事業への導入に向けた調査等が今年度からスタートしたところです。
さらに、昨年度の「公民協働プロジェクト検討プラットフォーム」の場において、金融機関等から、県内で民間事業者による観光地開発や再生可能エネルギーの創出などの大規模プロジェクトが計画される中、官民連携によりそれらを資金面等から後押しし、その実効性を高め、資金の好循環や地域への裨益につなげていくことが必要とのご意見をいただいたところです。
県としても、こうした取組を官民が連携して支援することは重要と考え、県内金融機関が今後新たに組成する官民連携ファンドに対して出資することにより、地域経済・社会の面的な活性化につながる民間の長期投資事業を資金面から積極的に支援してまいります。
第八点目は、防災・減災対策の推進についてです。
能登半島地震をはじめ、近年、全国的に自然災害が激甚化・頻発化している状況を踏まえ、県としましては、国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」等による有利な財源を最大限活用し対策を進めているところです。
5か年加速化対策終了後も本県に必要な施策に取り組めるよう、国土強靭化対策の継続と十分な予算の確保、地方負担の更なる軽減について、国に働きかけながら、引き続き県民の命と暮らしを守るため、事前の防災・減災対策を推進してまいります。
災害発生時には、避難者が速やかに必要な支援を受けられる体制を整備することが重要です。
このため、避難所の環境改善に資する備蓄資機材等の充実を図り、防災イベント等での普及啓発に利活用してまいります。
また、災害発生時の避難者情報を迅速に把握するためのシステムを開発し、県と市町村が共同でシステム運用することにより、避難所等において、避難者がその属性に応じた速やかな支援を受けられる体制を整備してまいります。
次に、原子力防災対策の推進についてです。
原子力防災訓練については、先月24日から25日に住民避難や、民間事業者による除雪が困難な場合を想定し、陸上自衛隊が道路除雪を行うなどの総合訓練を実施しました。今後とも、こうした訓練を繰り返し行うことにより、原子力災害発生時に備えた対応力のさらなる向上を図ってまいります。
原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備等については、先月29日、整備等の促進に向け、国との第2回会合が開催されました。今回の会合では、前回確認された優先すべき事業の考え方に基づき、整備箇所について確認するとともに、現況確認や工法の検討等の調査費用について、国が予算措置することが確認されたことから、関連する予算案を本定例会にお諮りしているところです。引き続き、早期の整備に向けて、国とともに取り組んでまいります。
また、PAZ及びUPZにおいて、避難により健康リスクが高まる方が屋内退避を行うための放射線防護対策施設の整備を進めるとともに、一般住民を含め自宅以外でも屋内退避が行えるよう、新たに、避難所となる学校の体育館等の放射線防護対策について国とともに調査・検討を進めてまいります。
加えて、能登半島地震における孤立地域の発生を踏まえ、新たに、PAZ及びUPZで孤立のおそれがある地域の指定避難所の備蓄物資や備蓄倉庫の整備を支援してまいります。
技術委員会における柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認については、今月12日に、報告書が県に提出されました。技術委員会においては、原子力規制委員会の柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関する設置変更許可の審査内容や、福島第一原発事故原因の検証結果、東京電力の核物質防護に関する一連の不適切事案等を踏まえて整理した、安全対策に関する22の確認項目について、東京電力や原子力規制庁から説明を受け、確認結果を報告書としてとりまとめていただきました。
県といたしましては、原発再稼働に関する議論を深めていただくよう、県民の皆様に情報提供、共有を図ってまいります。また、東京電力や原子力規制委員会には、原子力発電所の更なる安全性の向上に取り組んでいただきたいと考えております。
第九点目は、北朝鮮による拉致問題についてです。
拉致被害者やそのご家族の高齢化が進む中、いまだ拉致問題の解決に向けた具体的な進展が見られないことは本当に残念でなりません。
先月、第一次政権時に米朝首脳会談において拉致問題に言及した実績を持つトランプ米国大統領による第二次政権が発足しました。日本政府からは、米国と一層緊密に連携を図り、北朝鮮への働きかけを強めながら、全ての拉致被害者の一日も早い帰国に結び付けていただきたいと考えております。
また、今月13日には、知事の会として、林官房長官兼拉致問題担当大臣にお会いし、改めて、特定失踪者も含め拉致被害者の救出に向けて、早期に目に見える成果を出していだだくよう強く求めたところです。
県としましては、今後も、拉致問題の早期解決に向けた国への働きかけを行うとともに、世論喚起に向け、若い世代を含め、県民から関心を持ち続けてもらえるよう、市町村長の会や教育機関等と連携しながら、啓発活動に一層力を入れて取り組んでまいります。
この項の最後に、行財政運営についてご説明申し上げます。
先般お示しした中期財政収支見通しでは、能登半島地震への対応等により、今年度は財政調整基金を一時的に取り崩すこととしておりますが、令和7年度には国の財政措置等を踏まえ230億円まで積み戻すことを見込んでおります。
また、積み立てた県債管理基金を取り崩していくことで、令和13年度の公債費の実負担のピークに対応することができる見通しとなっております。
引き続き堅実に収支を見通しながら、持続可能な財政運営の実現に向けて取り組んでまいります。
以上、主要課題について順次申し上げましたが、それらも反映した令和7年度一般会計予算案は、1兆2,634億5千万円と、令和6年度予算に比べ、総額で1.8%の減となったところです。
次に、今議会に令和7年度当初予算案と併せて上程されました令和6年度補正予算案に関する議案等についてご説明申し上げます。
第36号議案は一般会計補正予算案でありまして、総額788億6,353万円の追加補正についてお諮りいたしました。
今回の補正は、エネルギー価格・物価高騰等の影響への対応や、投資事業等について令和7年度当初予算案と一体で計上するものです。
また、この補正予算に係る公共事業等について、繰越明許費を計上したほか、令和7年度に係る起工準備期間の確保等を図るため、いわゆるゼロ国債を7億400万円計上しております。
以上、補正予算案についてご説明申し上げましたが、その結果、補正後の令和6年度予算の規模は、1兆3,784億3,806万2千円となります。
次に、お諮りしております条例案件等のうち主なものについて、ご説明申し上げます。
第24号議案は、特別職報酬等審議会の答申等に基づき、特別職の報酬等の額を改定するため、第25号議案は、人事委員会勧告に基づく給与改定のうち、令和7年4月より適用となる一般職の職員の給料表等を改定するため、第27号議案は、障害の有無に関わらず全ての県民が自分らしく生きることができる共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別解消をさらに推進していくため、それぞれ、条例の制定及び所要の改正を行うものであります。
また、第34号議案は、あっせんの申立てについて、第35号議案は、包括外部監査契約の締結について、お諮りするものです。
以上、新年度における所信の一端と施策・議案の概要などについて申し述べました。何とぞ慎重にご審議のうえ、上程された各議案それぞれについて、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
2月27日 知事説明要旨
ただいま上程されました議案40件について、ご説明申し上げます。
第39号議案は、令和6年度一般会計補正予算案でありまして、総額710億8,119万2千円の減額補正についてお諮りいたしました。
このたびの補正予算は、令和6年能登半島地震からの復旧・復興を図るために必要な経費や、道路除雪費の所要額を計上するとともに、事務事業の執行見込みに基づく過不足調整等を行うものであります。
この結果、補正後の予算規模は、1兆3,073億5,687万円となります。
また、第40号から第58号までの各議案は、特別会計並びに企業会計に係る補正予算でありまして、それぞれ事業計画の最終見込み等に合わせまして、補正を行うものであります。
次に、その他の主な条例案件等について、ご説明申し上げます。
まず、第62号議案は、国の子育て支援に関する基金事業の実施期間に合わせて、新潟県安心こども基金の終期を延長するため、第63号議案は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和4年県北豪雨で被害を受けた河川等を特定都市河川等に指定するため、それぞれ、条例の制定及び所要の改正を行うものであります。
次に、第74号議案及び第75号議案は、指定管理者の指定について、お諮りするものです。
以上、各議案の概要につきましてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重にご審議の上、各議案それぞれについて、ご賛同賜りますよう、お願い申し上げます。
3月12日 知事説明要旨
ただいま上程されました議案4件について、ご説明申し上げます。
第79号から第82号までの各議案は、令和6年度一般会計及び港湾整備事業など特別会計に係る補正予算でありまして、それぞれ予算の繰越についてお諮りいたしました。
公共事業等の執行に当たり、設計や計画の変更、用地補償における調整などにより、一部年度内に完了できない見通しとなりました。
このため、一般会計においては707億1,919万3千円を、また、特別会計においても、それぞれ所要額を翌年度に繰り越すものであります。
この結果、本定例会の冒頭で議決をいただいた公共事業予算等に係る繰越と併せ、一般会計の繰越明許費の合計は、1,359億1,731万2千円となった次第であります。
何とぞ慎重にご審議のうえ、各議案それぞれについてご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
3月21日 知事説明要旨
ただいま上程されました議案6件について、ご説明申し上げます。
第83号議案は、令和7年度一般会計補正予算案でありまして、総額11億8,933万1千円の増額補正についてお諮りいたしました。
このたびの補正予算は、国の当初予算案修正に伴い、高校授業料無償化等への対応に要する経費を計上するものであります。
この結果、補正後の予算規模は、1兆2,646億3,933万1千円となります。
また、第84号議案は、高校授業料無償化に係る国の当初予算案修正に伴い、通信制の課程を除く県立高等学校及び中等教育学校の後期課程における授業料の特例について、所要の改正を行うものであります。
次に、第85号から第88号までの各議案は、いずれも人事に関する案件であります。
第85号議案は、教育長を任命するため、第86号議案は、監査委員を選任するため、第87号議案は、新潟海区漁業調整委員会委員を任命するため、第88号議案は、佐渡海区漁業調整委員会委員を任命するため、それぞれお諮りいたしました。
以上、各議案の概要につきまして、ご説明申し上げましたが、各議案それぞれについて、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
令和7年2月定例会・議会情報項目一覧へ
新潟県議会インターネット中継のページへ<外部リンク>
新潟県議会のトップページへ