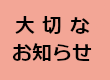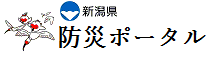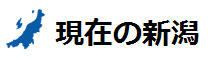本文
工房ではなく、工場(こうば)として伝統を守りつなげる 大湊文吉商店 大湊陽輔さん・菅沼樹さん
伝統を守りつなげること
昭和初期から続く屏風づくりに携わる担い手さんが加茂市にいます。
「加茂は箪笥で有名だが、その技術だけでは屏風が作れない。建具の技術が無くては作れないのです」
そう話す社長の大湊さんは、代表的な屏風をいくつも広げながら教えてくれました。
それぞれの屏風について熱く語ってくださった社長の大湊陽輔さん
大湊文吉商店は、屏風だけでなく仏具や組子など様々な木製品を製造販売していますが、創業は明治初頭、柿渋を和紙に塗った渋紙の製造卸からスタートしたそうです。その後昭和に入り、二代目の時代から表装屏風の製造卸が始まり、「紙」と「木」の融合商品を生みだしてきました。
その後、全国の家具店などを通じて販売されるヒット商品となったものの、ライフスタイルの変化により、商品の売れ行きにも変化が。
「今では、屏風の製造は国内でここだけ」と語る大湊さん。屏風の製造を続けるため、様々な工夫を続けられています。現場を案内してくださった開発担当の菅沼さんは、「職人技はもちろん大事であるが、従事する人たちが安全に効率よく製造を続ける上での日々の工夫と丁寧さが大事」と話します。皆が気持ちよく作業するための木粉集塵装置を整備するなどの工夫も施されていました。

「建具も組子も組んで製品にするところから逆算して、加工方法や形の設計を行います。加工のために道具も自作するのですよ」と、菅沼さんは工程ごとに様々な道具を見せてくれました。

「組み立てた時の寸法精度も考慮した設計力が大切なのです」大湊さんもそう語る。複数の加工した部品を組み合わせる製品づくりだからこそ、職人の感覚と図面による「見える化」による技能伝承も進めているそうです。
別室では、障子屏風の障子貼りの作業中でした。しわが入らないような丁寧な職人技が光る作業です

「互い違いになっている蝶番(ちょうつがい)だからこそ、屏風の開閉が美しくなる」と実演してくださった大湊さん
伝統の技術を活かした商品開発
大湊文吉商店では、ライフスタイルにあわせた新商品開発も盛んです。新たな商品開発は、菅沼さんが中心となり女性スタッフたちと商品開発会議と試作を行っているそうです。「途中のものを社長に見せると、いろいろコメントが入るので、開発がほぼ出来た段階で見せるようにしています」と、菅沼さんは笑いながら話していました。大湊文吉商店の雰囲気や働く人たちそれぞれの得意技がつまった開発の過程の一端が垣間見えた気がします。
組子の最初。ここからいくつもの形と商品アイデアが広がるそうです
ライフスタイルが変化する中、屏風の販売も変化しているが、最近では、キャラクターコラボや海外デザイナーとのコラボなど、時代に合った商品づくりを続けています。


にいがた産業創造機構の百年物語などのプロジェクトにも参加。海外展示会などにも積極的に出向いているそうです


買う人が様々な組子を組み合わせることができるカスタムパネルも新しく作った商品のひとつ
「ぼくたちは工房ではなく、工場(こうば)として、伝統を守りつなげているんです」時代に沿った商品づくりと同時に、時代に沿ったものづくりを続けられる社長の力強い言葉がとても印象的でした。
ユニット式和室「座・結界」の前で
(左から菅沼さん、大湊さん、加茂市商工観光課の髙野さん)
製品を購入するには
現在は、実店舗やオンラインショップにて購入可能
・ぽん酒館クラフトマンシップ<外部リンク>(新潟市中央区)
・家庭画報ショッピングサロン<外部リンク>
・I・E・Iオリジナルショップ<外部リンク>
・東京書芸館<外部リンク>
インフォメーション
株式会社大湊文吉商店
新潟県加茂市秋房1-26
TEL 0256-52-0040
HP<外部リンク> Facebook<外部リンク>
取材日:2023年8月1日










 01 足立茂久商店 足立照久さん
01 足立茂久商店 足立照久さん 02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん
02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん 03 吉田バテンレース 吉田節子さん
03 吉田バテンレース 吉田節子さん 04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん
04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん 05 須藤凧屋 須藤謙一さん
05 須藤凧屋 須藤謙一さん 06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん
06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん 07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん
07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん 08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん
08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん 09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん
09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん 10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん
10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん 11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん
11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん 12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん
12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん 13 西潟製陶所 押見くみこさん
13 西潟製陶所 押見くみこさん 14 岡田蝋燭店 岡田和也さん
14 岡田蝋燭店 岡田和也さん 15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん
15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん