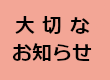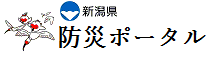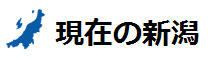本文
使い手と器の懸け橋になれるような工芸品を産む 西潟製陶所 押味くみこさん
幸せを届ける工芸品作り

60年前に作られたレンガでできた門柱
約160年という長い歴史を持つ窯元で、ご先祖の思いを大切にしながら、現代の生活にフィットする陶器を作り出している担い手さんが、ここ新潟市秋葉区の工房にいます。

工房兼ショップ「もえぎ陶房」
「ここは母方の実家で、よく遊びに来ていたので小さい頃から窯は身近な存在でした。『後継者がいなくて…』と話す祖母を見ていたのもあり、この道に進もうと思ったのも自然なことでした。」
新津焼を生産している西潟(にしがた)製陶所の押味くみこさんは、県外の大学で焼き物について学んだ後、叔父の跡を継いで6代目となりました。

おすすめのうさぎお猪口を持つ押味くみこさん
「全盛期の頃と比べると新津焼を作る窯は減ってしまいました。長い歴史や産地があることを知ってもらうために、これまでご先祖様が作り続けてきたものを守りながら、使う方と器の懸け橋になりたいです。」
そのように話す押味さんが作りだす陶器は、古くからの製法や原材料を守りながらも新しさを感じさせます。

ショップスペースには様々な新津焼が並びます
「『幸せをお届けしたい』というのが、製作する上での不変のテーマ。長年の修行が必要な伝統技法の世界で、苦労しながら出来上がったものは愛着も沸きますし、それがやりがいにもなっています。」



陶器のデザインは、普段生活している中で頭の中にフッと浮かんでくるのだそうです。
“自然”を相手にすること
新津は新潟市の中でも雪が多く振る地域であるため、冬場の製作は特に気を使います。

ひび割れてしまった分は粘土に戻して一からやり直します
「冬の時期は乾燥が進みにくいので管理が大変。途中でひび割れが起きると次の焼く工程に進めません。」
時には凍って割れてしまうこともあるそうです。

しっかり乾燥したら窯で焼きます
新津焼を生み出すために自然を相手にして動かなくてはならないことは大変ですが、楽しい面もあるのだとか。
「地元の樹木の灰で作った釉薬を使っていますが、同じ木でもその時々によって、焼いた時に色が微妙に違っていておもしろいんですよ。」

押味さんの推しは松。深い緑が入ります
焼くまで分からない楽しさは、自然由来ならではですね。

材料の樹木は工房の庭からも採取します
伝統を大切にしながら今らしく

三点模様の入った陶器
新津焼の特徴の1つである三点模様があしらわれた陶器に使われる釉薬は、ご先祖が使っていたものを使用しています。
「長らく調合方法が分からずにいたのですが、5年ほど前に偶然、釉薬の残りと調合帳を発見したことで再び三点模様の新津焼の製作が出来るようになりました。」

約100年前の昭和7年頃に作られた調合帳

釉薬などと一緒に入れられていた新聞にも時代を感じます
今後は伝統の三点模様にちなんだ工芸品も製作していきたいという押味さん。
「全盛期にたくさん作られていた三つ足の植木鉢や、三点模様の器など、先祖が好んでいた3の数を大事にして、今の感覚で喜んでもらえたり受け入れてもらえるものをこれからも生み出していきたいです。それと同時に、古くから作られてきた縁起物なども、大切に作り続けていきたいと思っています。」

資料スペースには貴重な昔の工芸品が置かれています

植木鉢作りに使われた機械

家紋の粘土型。以前は安田瓦鬼瓦につけるためのものを生産していたそうです
自然と調和しながら製作に取り組む押味さんの工芸品は、これからも多くの人の心をときめかせ、温かくしていきます。

製品を購入するには
事業者の工房併設のショップやECサイト<外部リンク>で購入可能
インフォメーション
西潟製陶所
新潟県新潟市秋葉区滝谷本町2-5
TEL 090-8252-1856
HP<外部リンク> Twitter<外部リンク> Facebook<外部リンク>
陶芸体験や教室への参加も可能です。(※要予約)
詳細は事業者HPをご覧ください。
取材日:2023年1月19日



 01 足立茂久商店 足立照久さん
01 足立茂久商店 足立照久さん 02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん
02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん 03 吉田バテンレース 吉田節子さん
03 吉田バテンレース 吉田節子さん 04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん
04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん 05 須藤凧屋 須藤謙一さん
05 須藤凧屋 須藤謙一さん 06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん
06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん 07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん
07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん 08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん
08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん 09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん
09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん 10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん
10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん 11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん
11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん 12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん
12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん 13 西潟製陶所 押見くみこさん
13 西潟製陶所 押見くみこさん 14 岡田蝋燭店 岡田和也さん
14 岡田蝋燭店 岡田和也さん 15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん
15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん