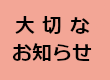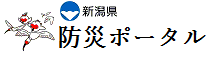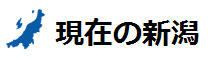本文
老若男女に愛される工芸品を生み出す 藤岡染工場 野﨑あゆみさん
歴史をこれからも繋ぐ
白鳥が飛来する瓢湖の近く(阿賀野市旧水原町地域)に、越後本染注染手拭の担い手である『藤岡染工場』があります。
ここでは、江戸時代初期に大阪府堺市で確立された『注染』(ちゅうせん:重ねた布の両面から染料を注ぐ技法)の技法を大正時代初期から取り入れ、現代まで脈々と受け継いでいます。

手拭だけでなく半纏等の染物も作っています
「これまでの先代達が繋いで来た歴史を、これからも途切れさせることなく残していきたいと思っています。」
そう話す野﨑あゆみさんは、大学時代は染物について学ばれ、製品作りに携わる仕事を経て現在は広報を担われています。

野﨑あゆみさんと代表の藤岡修さん
野﨑さんが持つのは店を構える水原地域をイメージしたデザインの手拭です
「大学で染物を専攻したものの、最初は家業に入るつもりはありませんでした。でも『藤岡染工場』の手仕事がやっぱり好きだったのですね。」

手拭のデザインの型紙。くり抜いた部分に糊を乗せることで染料から生地を保護し、染まらない部分が生まれます
職人の経験と感覚が鍵
手拭は30~40枚分の長さの1枚の生地を重ねて染めるため、1つの失敗でこれまでの作業が全て水の泡になってしまいます。

糊置きする作業場。右下にあるのが糊です
「例えば、染めない部分を保護するための糊に混ぜる水の割合を間違えると染めた時ににじみが出てしまい、意図する図柄になりません。1つ1つの作業を集中して行います。」
作業を失敗しないためには、職人1人1人のこれまで培われた経験や感覚が鍵となります。

型紙の上から糊を乗せる様子

布地に綺麗に糊がつきます。この作業をズレがないよう繰り返していきます

重ねた布の表裏から染料をかけていきます

染めた布を丁寧に水で洗います
手拭作りに新しい風を
大きい事業者の場合、各作業は分業制の所が多いですが、ここではデザインから仕上げまで職人が一貫して担当します。

綺麗に包装されていく手拭
「最初から最後まで一連の製品作りを担うので、製品に対する思い入れは大きく、お客様に『可愛い』と言ってもらえると喜びもひとしおです。」
自社で一貫生産を行う特徴を活かし、年に2~3回程度、若手の職人たちによる手拭のデザインコンペを実施しているそうです。
「20~40代の職人それぞれが自分のデザインを持ち寄ります。優勝すると実際に製品化して販売出来るんですよ。」
また、長岡造形大学の学生とコラボした手拭を毎年販売するなど、染技法の伝統を大切にしつつも、若手の新しいアイディアを取り入れてより良い物作りを行っています。

学生デザインの手拭
藤岡染工場で生産される越後本染注染手拭はどの柄も愛らしく、使う方の年代を問いません。昔からある手拭を古く感じさせないのは、このような『新しい風』を大切にしているからなのですね。
「手拭は手を拭いたりする他にラッピングやインテリアの壁掛け等、幅広い使い道があります。お客様の生活の様々な場面で、越後本染注染手拭を使っていただけたら嬉しいですね。」

並べて干された手拭
作業場に干された、染め上げられたばかりの手拭が風を受ける光景は、まるで様々な可能性を秘めた手拭自身のこれからの未来にわくわくしているようにも感じられました。
製品を購入するには
店舗やECサイト<外部リンク>にて購入可能な他、オーダーメイドも可。
インフォメーション
藤岡染工場
新潟県阿賀野市中央町2-11-6
TEL 0250-62-2175
HP<外部リンク> Facebook<外部リンク> Instagram<外部リンク>
取材日:2022年6月16日



 01 足立茂久商店 足立照久さん
01 足立茂久商店 足立照久さん 02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん
02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん 03 吉田バテンレース 吉田節子さん
03 吉田バテンレース 吉田節子さん 04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん
04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん 05 須藤凧屋 須藤謙一さん
05 須藤凧屋 須藤謙一さん 06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん
06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん 07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん
07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん 08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん
08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん 09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん
09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん 10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん
10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん 11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん
11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん 12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん
12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん 13 西潟製陶所 押見くみこさん
13 西潟製陶所 押見くみこさん 14 岡田蝋燭店 岡田和也さん
14 岡田蝋燭店 岡田和也さん 15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん
15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん