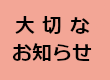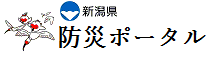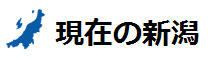本文
多くの人との関わりで生まれる和紙 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん
商店街の中で市と取り組む和紙作り

実はこの建物は以前、銀行だったとか
かわいいリスと触れ合える加茂山公園のほど近くにある商店街の中に、加茂紙を生産する『加茂紙漉場』があります。
中には、和紙の原料である楮(こうぞ)の外皮から汚れた部分を取り除く「チリ取り」を行う担い手さんの姿がありました。

この作業ではお湯を使うとのこと

取り除かれた分も和紙として余すことなく使います
「ひとつひとつ手作業で行うので、この量だと3日くらいかかります。」
冷たい水だったらもっと大変ね、と笑う笑顔が素敵な鶴巻由加里さんは、現在、加茂紙の唯一の担い手さんです。
明治の終わり頃に新潟県の和紙生産額の内、約40%を占め首位を誇った加茂紙は、平成5年に一旦生産を終了したものの、保存会の働きかけで平成23年に加茂市が中心となって和紙作りを復活させました。その時に、技術継承に名乗りをあげた10人の内の1人が鶴巻さんで、現在は市の臨時職員として加茂紙作りに携わっています。

壁には以前の生産者が作業を行う様子の写真がありました
「市報を見ていたら募集のお知らせを見つけて。元々和紙作りには興味があったのもあり応募したんです。」

チリ取りをした楮を叩いて繊維をほぐす鶴巻さん
その前は長らく主婦をされており、和紙作りの知識に関してはまさに白紙の状態。加茂紙のことや歴史も全く分からなかったそうです。そこから約10年、和紙作りを行ってきました。
「スキルや知識がゼロの状態からスタートしているので、10年とは言えまだまだ自信が十分あるとは言えないです。」

左から渋谷さん、鶴巻さん、髙野さん
加茂紙漉場で実際に和紙作りを行う鶴巻さんをサポートするのは、加茂市教育委員会 社会教育課の渋谷肇さんと、加茂市役所商工観光課の髙野竜弥さんです。
「新潟県が指定する伝統工芸品の制度と、その指定工芸品の募集をしていることを知り、県内外へ広く加茂紙をアピールできると思い申請しました。」
原料となる楮(こうぞ)やトロロアオイの栽培作業にも参加しているそうです。
和紙はサスティナブル
鶴巻さんが作る和紙の中には、真っ白なものだけではなく、模様や色が入ったものもありました。一体これはどうやって作っているのでしょうか。

黒い点々は墨によるものです
「実はこれは、書き損じた和紙を再利用して漉いているんですよ。墨などの黒が混ざって、このような風合いの和紙になります。」
また、「チリ取り」の工程で除かれたチリだけを使って紙を漉くこともしています。
元々加茂紙が盛んに作られていた七谷(ななたに)地区は古紙を仕入れて『ちり紙(今でいうティッシュペーパー)』を作る生産者も多くいたそうです。
漉きなおしを繰り返すと強度は弱くなりますが白くなり柔らかな紙に仕上がります。
「最初は『もったいない』という気持ちから始めましたが、かえってこのテイストの和紙を好まれる方も多いです。和紙は繰り返し漉くことができるので、現代のSDGsの考え方にも合っていますよね。」
購入した和紙で書き損じてしまったものや、端っこの残りなどがあれば、加茂紙漉場へ持って行くと、引き換えに「ちょっとしたプレゼント」をしてもらえるそうですよ。

アーティストとのコラボ作品
加茂紙は大きなサイズの3×6(サブロク)版(約91cm×182cm)を1人で漉くのも特徴の1つです
多くの人々に支えられて
加茂紙漉場では、より多くの人々に和紙作りに関わってもらいたいと考えています。
「去年は来店されたお客さんに『花を楽しんだ後は、最後に残る根っこを持ってきてくださいね』と、原材料の1つであるトロロアオイの種をお配りしていました。」

瓶に入ったトロロアオイの種
実際に、根っこを持って再来してくださる方もたくさんいたそうです。

工房内には和紙作り体験に参加した地域の小学生からのお礼のお手紙がありました

近くの青海神社では加茂紙を使った御朱印もいただくことができます
「定期的に行っている和紙作り体験だけではなく、古紙を持ってきていただいたり、原材料の栽培に携わってもらったりと、色々な形でたくさんの方から参加してもらうことで、加茂紙の伝統を繋げていきたいです。」
多くの人に支えられながら、今日も鶴巻さんは和紙を漉いていきます。
製品を購入するには
工房にて直接購入可能な他、一部商品を加茂市公民館や図書館で販売中。
インフォメーション
加茂紙漉場
新潟県加茂市上町1-22
TEL 0256-52-4184
HP<外部リンク> Instagram<外部リンク>
取材日:2023年1月10日



 01 足立茂久商店 足立照久さん
01 足立茂久商店 足立照久さん 02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん
02 小国和紙生産組合 今井宏明さん・千尋さん 03 吉田バテンレース 吉田節子さん
03 吉田バテンレース 吉田節子さん 04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん
04 小千谷煙火興業 瀬沼 輝明さん 05 須藤凧屋 須藤謙一さん
05 須藤凧屋 須藤謙一さん 06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん
06 長場鬼瓦工場 長場龍也さん・彩香さん 07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん
07 庵地焼旗野窯 旗野麗子さん・聖子さん・佳子さん 08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん
08 大谷内和紙保存会 小柳正道さん 09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん
09 藤岡染工場 野﨑あゆみさん 10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん
10 磯野紙風船製造所 磯野成子さん 11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん
11 十日町友禅 吉澤さん・青柳さん・関口さん・越村さん 12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん
12 加茂紙漉場 鶴巻由加里さん 13 西潟製陶所 押見くみこさん
13 西潟製陶所 押見くみこさん 14 岡田蝋燭店 岡田和也さん
14 岡田蝋燭店 岡田和也さん 15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん
15 大湊文吉商店 大湊さん・菅沼さん