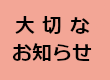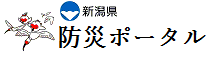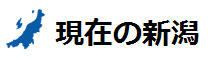サイト内検索
ページ番号を入力
本文
カンピロバクター
特徴
- 家畜、家きん、ペット(イヌ、ネコ)、野生動物、野鳥等の腸内に生息しています。
- 主に食肉(特に鶏肉)に付着しています。
- 乾燥状態や熱に弱い一方で、低温では長期間生存します。
- わずか100個程度の菌でも摂取すると発症します。

出典:内閣府ホームページ(https://www.fsc.go.jp/sozaishyuu/shokuchuudoku_kenbikyou.html)
症状
- 発熱等の前駆症状の後、吐き気、腹痛、下痢等があります。
- 潜伏期間は一般に2~7日間(平均2~3日)
- 回復後、2~4週間排菌がみられることがあります。(長い場合は、数ヶ月に及ぶ)
- まれに感染後に神経疾患であるギラン・バレー症候群を発症することもあります。
- ギラン・バレー症候群とは
- 急激に手足の筋力が低下し、症状が進行する末梢性の多発性神経炎が数週間持続し、その後、ほとんどの場合は寛解する。カンピロバクター感染も同症候群を誘発する要因の一つとして考えられているが、その機序等は未解明。
原因となりやすい食品
 肉料理(特に鶏肉)、バーベキュー等
肉料理(特に鶏肉)、バーベキュー等- 飲料水(井戸水、湧き水)
- 二次感染を受けた食品(サラダ等)
予防のポイント

- 調理器具を使い分けましょう(肉用、野菜用等)。使い終わった調理器具は洗浄・消毒し、十分乾燥させましょう。
- 焼肉をする場合は、専用トングを使うか、生肉を扱う箸と食べる箸を別々にしましょう。
- 生肉を扱った後は、必ず手を洗いましょう。
- 飲料水(井戸水、貯水槽)は必ず塩素消毒しましょう。
県内の発生状況
- 食中毒統計のページをご覧ください。
消費者の皆様へ
- 肉類を食べるときは、十分(中心部が75℃・1分間以上)に火を通しましょう。
- 生肉を食べるのは避けましょう。
- 焼肉をするときは、「肉を焼く箸」と「食べる箸」を別にしましょう。
- サラダや調理済み食品は、生肉や生肉からしみ出した液と接触しないようにしましょう。
- 肉類の調理に使用した包丁やまな板などの器具類は、使った都度よく洗浄した後に消毒しましょう。
- 飲料水(井戸水、貯水槽)の塩素消毒を徹底しましょう。
営業者の皆様へ
消費者の皆様への注意の他、次の点に気を付けてください。
- お客様自身が肉を焼く場合は、必ず「肉を焼く箸」と「食べる箸」を別に用意し、使い分けを勧めましょう!
啓発資料
リーフレット「肉の加熱ず足による食中毒に注意!」 [PDFファイル/1.13MB]


カンピロバクターによる食中毒についてさらに詳しい情報は、カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)(厚生労働省ページ)<外部リンク>をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)